静謐な空間が提示する豊穣な想像力の可能性
1995年の開館以来、絵画、彫刻からファッション、建築、デザインなど、ジャンルを超えて国内外のコンテンポラリー・アートに関わる事物を紹介してきた東京都現代美術館。
いま、同館でははじめて、平成生まれの作家の個展が開催されている。
アーティストは、EUGENE STUDIO(ユージーン・スタジオ)。
1989年にアメリカで生まれた寒川裕人(Eugene Kangawa)による、日本を拠点にするアーティストスタジオである。
2014年のロンドンのサーペンタイン・ギャラリーへの作品提供、2017年の資生堂ギャラリーでの個展、2020年の金沢21世紀美術館での展覧会への参加をはじめ、アメリカの現代SF小説家ケン・リュウとの共同制作、さらには2021年に短編映画をアメリカで発表するなど、その作品は、絵画、立体、インスタレーションから映像制作まで幅広い。2019年に国立新美術館で発表された、完全な暗闇における能のインスタレーション「漆黒能」をご記憶の方もいるだろう。
2021年に発表された短編映画は、ヒューストン国際映画祭、ブルックリン国際映画祭、パンアフリカン映画祭など、アカデミー賞公認国際映画祭を含む10以上の国際映画祭での受賞やオフィシャルセレクションへの選出が続いているという。
自由な発想から生み出される多彩な表現で、国際的な注目が高まっているこのアーティストの国内公立美術館での初の大規模個展でもある。

ベルリンの壁崩壊の年に、父の仕事の関係でアメリカに生まれた寒川は、その後、兵庫県宝塚市に移り、6歳の時に関西・淡路大震災に遭う。大学時代には闘病生活を送っていた母の死を経験し、その翌年、2011年には東日本大震災が発生した。
小学生のときの1か月にわたるヨーロッパ旅行や、事典や図鑑が大好きだったという彼は、世界の事象から個の体験まで、さまざまな出来事をその眼でとらえてきた。
一方で、政治や社会学に興味を持ち、人工知能の研究が進む今に、あえて「わからないこと」を手がけることに可能性をみて、アーティストになることを選択したそうだ。
そんな寒川は、自身が生まれた時代・世界をみつめ、自身をとりまく環境やそこで生起するもの・ことをみつめ、常に思考する。
そのまなざしと感性が生み出す作品と空間は、“見えないもの”を可視化するというスタンスに貫かれて、「現実」への再認識、「信じられるもの」への問いかけ、「他者」との共有・共生の可能性/不可能性などを提示しながら、みる者にも改めて考え、想像することをうながしていく。
はじまりは真っ白なカンバス、〈ホワイトペインティング〉。
抽象画か、と思いきや、このシリーズは、彼が世界各地を訪ね、1枚につき100人ほどの人々に接吻してもらったもの。愛や信仰という見えないものを視覚化した彼の代表作は、礼拝の対象として、移動する建築ともたとえられ、高い評価を得た。
会場では、同じく持ち運べる信仰の対象として知られる19世紀末のロシア正教のイコンとともに展示される。

右下:同 展示風景から
美術批評家 デイヴィッド・ギアースから「愛と記憶にまつわる移動式の礼拝建築」と評された本作。絵画の枠を超えて、ミニマムな構造物、あるいは建築物として展示される。
そこから、本展タイトルを象徴する作品《海庭》へ。
同館の地下2階から地上階まで吹き抜けの空間に“海”が出現している。周囲は鏡で覆われて、壁に沿って歩くと自身の姿がさざ波に揺れる水面とともに無限に反復していく。
この空間が存在する地が海抜0m以下であることからインスピレーションを得た作品は、豊穣と脅威をもたらすとともに生と死の源としての「海」を、みる者に想起させる。
外光がそのまま入り、時間とともに刻々と表情を変える大規模なインスタレーションは、スケールにおいても、美しさにおいても圧巻だ。


「実際には未発見の海というものはこの世界にはありませんが、想像のなかの海はまだまだ無限に広がる」と述べる寒川は、豊穣と脅威をもたらす「海」に二項対立の先にある未来を提示しようとする。
自然の海のイメージは、〈レインボーペインティング〉の部屋で、「人の海」へとつながっていく。
一見、淡く柔らかいグラデーションを持つ油彩画のストイックな空間。しかし近づくと、画面は無数の点描で覆われている。寒川はひとつひとつの点を人に見立て、群衆を、多彩を表す“レインボー”に描き出すのだ。

視線をそらすと白く滲みそうな画面はぜひ近寄ってみて! ひとつひとつ微妙に異なる色の点々が大きな「虹」を構成していることがわかる。《群像》、《人の世》、《あなたはどこに?》と付されたタイトルとともに、それぞれの差異がつくりだす微妙な色面は、国や地域、社会を構成している個と集団について考えさせる。
多様な人間の存在する地上を取り囲むのは自然とさまざまなモノ。
次の部屋では、自然を独自の手法で写し取ったペインティングに囲まれて、卒業制作のひとつが紹介される。

真鍮に特殊な加工を施して、鉛筆や油絵具、オイルパステルを用いた絵画作品〈私にはすべては光り輝いて映る〉は、自然の中で、時とともに移り変わる光や風景、そして自身の視線の動きをトレースするように、複数のパースペクティヴが幾重にも重ねられている。
真鍮の輝きの中に浮かび上がる風景は、みる角度によって微妙な陰影をまとい、陽炎のように揺らめく。それは、まさに時間をそのまま封じ込めたようにも感じられる。

描かれた風景は、ときに日本画を思わせ、ときにモネの睡蓮を連想させ、ときに中世の「メメント・モリ」へとつながっていく。移りゆくものを映すもの、そしてそれらを写したもの、地と図のヒエラルキーはあいまいになり、「みる」ことと「認識する」ことへの反省をうながす。

スポーツが制度化される前の身体と思考の高揚やそこに生成される共同体を可視化することを、“盤上のスポーツ”といわれるチェスと、“セッション”を象徴するドラムに表した《あるスポーツ史家の部屋と夢 #連弾》は、「競争しつつ共創すること」の非言語的な対話を試みたリサーチとワークショップだったという。
チェスに創造の愉しみを見いだしていたデュシャンを想起すると同時に、JAZZのような即興とコードの競演の緊張感を感じさせる。

「競争と共創、争うこととともに創ることへ、というように、既存のルールや道具をひとつのガイドとして用いつつ、異なる自由なコードに変換される状態をみてみ」るというコンセプトから生まれた本作は、決められたものを援用しながら決められていない何かができ上がる、人間の創造性を追求した実験といえるのかもしれない。
寒川の思考はさらに進む。
個と世界の成り立ちについて問いかける空間では、さまざまな数の面を持つサイコロが無作為に転がった彫刻作品《この世界のすべて》を、鮮やかな翠色の色面が濃淡をつくる絵画作品《私は存在するだけで光と影がある》が囲む。
もっとも原始的な乱数発生器としてのサイコロは、その面と数によりほとんど無限に近い組み合わせの可能性を示唆する。生命誕生の奇跡的な可能性と数字というデジタルなものの偶然性が重なった時、「世界」がそこに提示される。
壁面の絵画は、翠色の染料を塗った紙を多角柱にして数週間太陽にさらし、褪色の原理を利用して生み出された。紙自体の陰影で成立したそれらは、時間と太陽との共同制作ともいえよう。平面と立体の間を往還してその境を無化しつつ、ものごとは存在そのものが光と影をあわせ持つことを体現した。

24面体から120面体、1/1などさまざまな形、大きさのサイコロを数十個、展示ごとに転がしておくため、同じ展示になることはゼロに等しい。幾何学的な要素が無限に近い可能性を持ち、生命の有機性に接続されるのが興味深い。
翡翠を思わせる絵画作品もまた、作家の意図と偶然性が生み出す、似て非なるそれぞれの唯一性を獲得している。日焼けというシンプルな自然原理が、「存在」についての深い思索をあざやかに提示する。

一室に大きく展開するのは、《善悪の荒野》だ。
映画ファンならば見覚えがあるだろう、スタンリー・キューブリック監督のSF映画『2001年 宇宙の旅』のラストシーンに出てくる白い部屋が原寸大で再現されるが、それらは破壊され、焼かれ、風化した姿で現れる。
地球外の知的プログラムともいえる「モノリス」が用意したこの部屋は、人類を進化させるテクノロジーの象徴だ。破壊された情景は、科学と技術により「進化」する未来像への「NO」となり、キューブリックが映画に秘めた皮肉と呼応する。同時に、裏側のハリボテを見せることで、映像やイメージが持つ虚構性も強く感じさせる。

展示風景から

右下:同 展示風景から
廃墟の風景は、過去を想起させる。しかし、その舞台は、近未来を描いた映画のラストシーンの情景。まるで標本のようにガラスケースに収められた作品は、過去と未来を封じ込めて、現在に提示されることで、みる者にとって実際につながっている未来へのまなざしを喚起する。同時にセットであることも意識させ、リアルとフィクションの関係をも宙づりにする。
何か善で何が悪か?
破壊されてなお、荒涼とした美を放つこの作品の前でも、みる者はまた、二元論の先について考えさせられる。
ホワイトキューブの各部屋から一転して、暗闇の中にほのかな光を発するのは、《ゴールドレイン》。
極小の金銀箔の粒子が降り注ぎ続けるインスタレーションは、まさに黄金の雨となって静かに、しかし、鮮烈な印象を与えて降っている。光をあてられることで見えるようになったその降下は、細くなったり、塊として落ちてきたり、常に変化して、一瞬たりとも同じ形にはならない。
そこに存在しているのに見えていないもの、人知ではコントロールできない予測不可能なものへの深い思索を導く静謐な空間は、時を忘れて見入ってしまう。

右:ユージーン・スタジオ 《ゴールドレイン》2019年 作家蔵 ©Eugene Kangawa
この作品について、作家は「生と死の澱(おり)、生命のよどみのようにも見える」と述べている。間断なく、同じ形なく降り続ける金の雨に、あなたは何を見いだすだろうか。
新作の映像作品《Our Dreams | 夢》は、ドビュッシーのピアノ曲『夢想』を遠く離れた2人の奏者が「空弾き」する情景がつなぎ合わされる。
想像の中で弾きつがれていく夢。
それは、新型コロナ下、接触や協働が困難になった現状において、その断絶を示すと同時に、わたしたちの想像の力がつながりを保てる大きな力であることを強くメッセージしているように思える。

そして、本展の特別な新作、彫刻作品《想像 #man》へ。
一筋の光もない真っ暗な展示室に置かれた彫像は、制作も暗闇の中でなされ、制作者自身もみていない。運搬・展示にあっても一切みられないそうだ。
永久に「見えない」ものとして制作された作品と展示空間は、手さぐりで進み、手で確認するしかない。
その体験は、「見えない」ことへの意識を覚醒させ、また暗闇というものに感じるさまざまな感情を引き出し、実像を触覚から想像するしかない、どうやっても(明確に)知ることができない存在を認識させる。
作家が「〈ホワイトペインティング〉、《海庭》、〈レインボーペインティング〉などが明るい光の中にある“おもて”だとすると、《想像 #man》は本展覧会の裏側を一手に担う作品だと思う」と述べるこの作品、時間入れ替え制の整理券が配布されるので、ぜひ時間を取って会場で体験してほしい。
限りなく静かに、そして美しく、複雑な世界の「在る」を考えさせるユージーン・スタジオの作品空間。
それは、深い思索と哀しみをたたえつつ、あらゆる二元論を超えたその先に、未来への希望の可能性、共生のための「想像力」を提示する。
「見えないものを想像する力は、多様性や共生への理解を前進させる力」(寒川)
彼が、個の名前ではなく、“スタジオ”として、さまざまな協働を想像させるアーティスト名で活動していることも、この信念に由来するのだろう。
これからの創造にも期待が高まるユージーン・スタジオの、これまでを堪能できる空間。
ぜひその眼で、感覚で、「体感」してほしい。
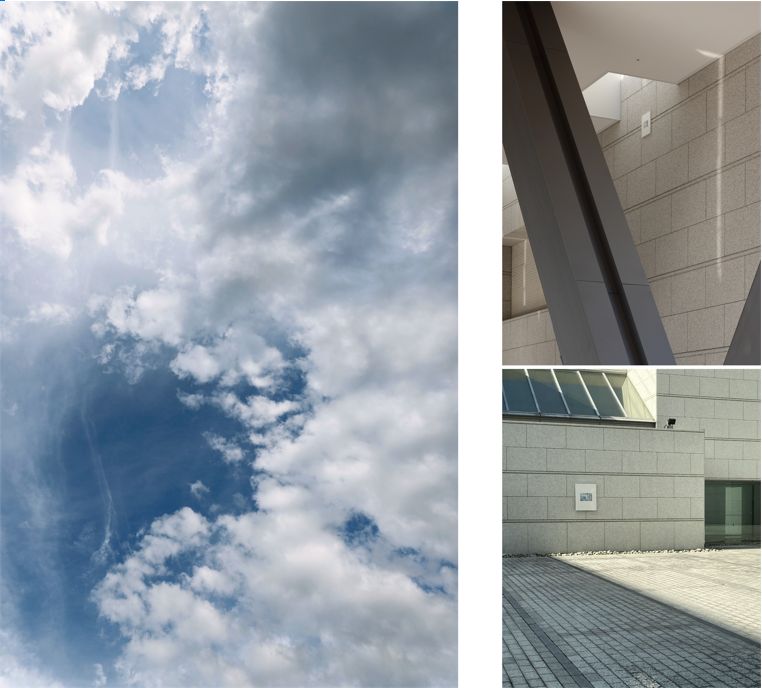
右:同 展示風景から
約8㎞にわたって点在した36名の人々が、一斉に空を見上げて撮影したものをつなぎ合わせた新作の写真作品。すべてを合わせると、地上で一人では観察できない水深約3000m地点から見上げた空の写真になるそうだ。本展では、個々の空が館内のあちこちに点在する形で展示される。展示室内にとどまることなく日常と地続きであること、それぞれの存在が共にあることではじめてひとりの視点では得られない視野を獲得できることを伝える美術館のメッセージが込められる。そしてつながりを想像することも、おそらく含まれているのだろう。

展覧会概要
『ユージーン・スタジオ 新しい海 EUGENE STUDIO After the rainbow』
東京都現代美術館 企画展示室地下2F
新型コロナウイルス感染症の状況により会期、開館時間等が
変更になる場合がありますので、必ず事前に展覧会ホームページでご確認ください。
会 期:2021年11月20日(土)~2022年2月23日(水・祝)
開館時間:10:00-18:00 (入場は閉館の30分前まで)
休 館 日:月曜日(2/21は開館)
入 館 料:一般1,300円、大学生・専門学校生・65歳以上900円
中高生500円、小学生以下無料
問 合 せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)
展覧会サイト https://www.mot-solo-aftertherainbow.the-eugene-studio.com





