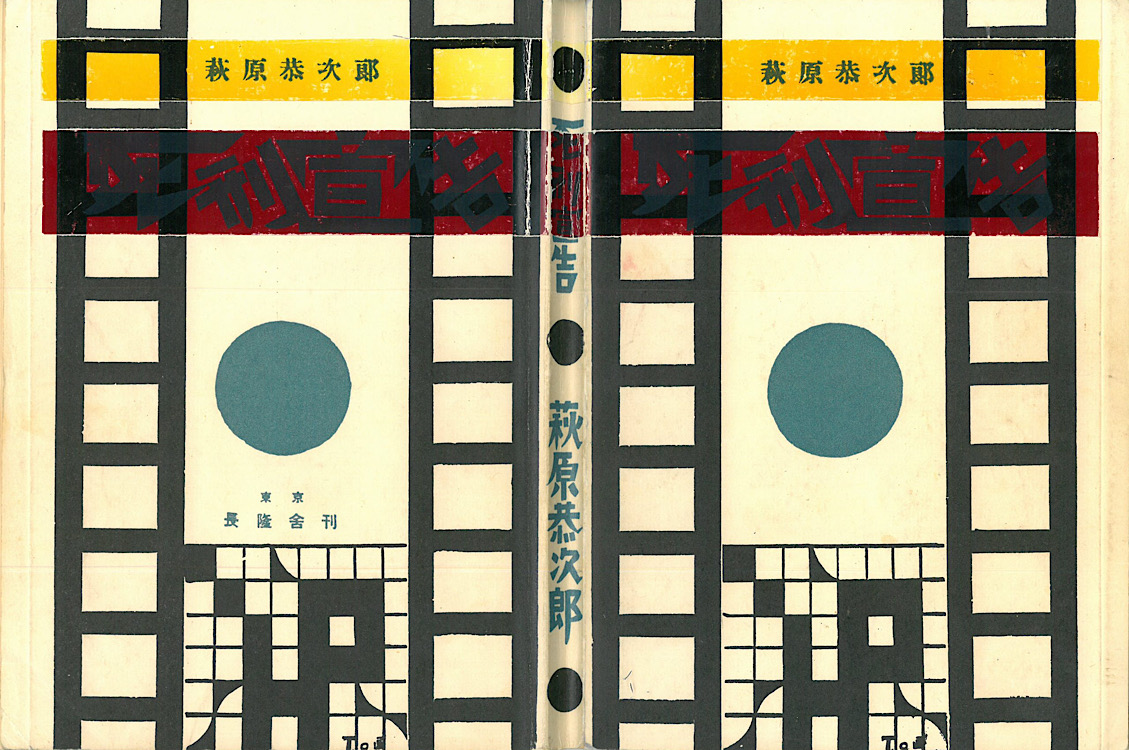2023年に生誕1250年を迎える空海。これを記念して、新連載「空海 祈りの絶景」がスタートいたします。
写真家・堀内昭彦氏と文筆家・堀内みさ氏が、空海ゆかりの地を巡りながらその偉大さに迫ります。
#0 プロローグ
濃い霧に包まれて、前が見えない。

深い静寂、凜とした空気。
久しぶりに訪れた高野山は、うっすらと雪に覆われていた。

標高約800メートル。周囲を1000メートル級の山々に囲まれた和歌山県の山上に広がる高野山は、弘法大師空海によって開かれた真言密教の聖地。なかでも奥之院には空海のご廟所があり、今も朝と昼の2回、心づくしの料理が日々欠かさず捧げられている。空海は、今もこれからも永遠に生きて瞑想を続ける、そう信じられているのだ。

長年西洋音楽のジャンルで仕事をしてきた私たち夫婦が、音をキーワードに日本文化を再発見する旅を始めて十数年。その間さまざまな神社仏閣を訪ね、奉納される音に耳を傾けては多くの方々に話をうかがい、祈りの姿を撮影させていただいてきた。アイヌの歌や踊りに惹かれ、現地の古老から、その背景にある祈りの心について話をうかがったこともある。空海への興味は、そんな日々の中でごく自然に湧き起こってきた。
真言宗の宗祖、空海は、奈良時代末期の宝亀5年(774)に讃岐(現在の香川県)で生まれ、承和2年(835)に入定(永遠の瞑想に入ること)した。

空海には4つの名前がある。幼名は「真魚(まお)」(フルネームは「佐伯直真魚(さえきのあたいまお)」)。出家してからは「空海」という僧名になり、その後密教の教えを学ぶため中国の唐へ留学したときに、師である恵果から「遍照金剛」という名を授けられた。さらに没後86年目には生前の功績が称えられ、朝廷から「弘法大師」という最高の称号である大師号を賜っている。

もっとも、この大師号は最澄や法然、親鸞、道元、日蓮などにも授けられている。それでも「お大師さま」といえば空海。そう思う人がほとんどなのは、空海の死後、土地それぞれの民間信仰と結びつき、あたかもスーパーマンのような伝説が流布したことが一因にあるのだろう。個人的には、四国の一部の区間ではあるものの歩き遍路を体験してからは、自然と「お大師さま」という言葉が口をついて出るようになった。

(右)四国八十八箇所霊場第21番札所 太龍寺
空海ゆかりの地の多くは、特に若き日の無名時代に修行したと伝わる場所は、いずれも思わず歓声を上げてしまうような絶景ばかり。


一説では15歳で都に出て、18歳で大学に進学。だが、官僚になるべく儒教などを学び始めたものの、空海は1年あまりで中退し、吉野や大峰山系、さらに四国の山々にこもって山林修行に身を投じたとされている。将来を約束された道を捨て、優婆塞(在家のままで仏道修行に励む人)となって自然の中で生き方を模索した空海。今もゆかりの地に立つと、空海も見たであろう風景が眼前に広がる。




さまざまなゆかりの地を巡り、あるときは満天の星を仰ぎながら、この世界に満ち満ちている聞こえない音について考えたり、

あるときは、ひっそりと息づく小さな生命に、ものごとの真理の一端を感じたり。



土地に積み重なる祈りの記憶にも想いを馳せた。

もっとも、そんな体験は、どれもいわばジグソーパズルの一片。今後どんな全体像を自分たちが描けるか、今は何もわかっていない。なにせ、巨大な世界を内包する空海である。時間をかけても、すべてを組み立てられないまま終わる可能性も大いにある。
だが、今一度ゆかりの地に足を運び、新たな欠片を拾いつつ現地の方々の言葉に耳を傾けることで、一筋の光が見えてくるかもしれない。むしろそんな文献や資料からこぼれ落ちたものをこそ丁寧に掬い取り、その過程を大事にしたいと思う。
漂う霧は現れては消え、消えては現れる。空は少しずつ明るくなり、頭上で鳥が鳴き出した。

空海は晩年、都に住む友人に、高野山での生活に何か楽しいことがあるのかと手紙で尋ねられ、春には春の、秋には秋の花々が心を慰め、夜明けの月や朝の風が心を洗ってくれると書いている。そして、山の霞を吸って心を養っていると。
巨大な人物、空海の源は、この日本という国の自然の中にあるのではないか。今は漠然と、そんなことを感じている。

堀内昭彦
写真家。ヨーロッパの風景から日本文化まで幅広く撮影。現在は祈りの場、祈りの道をテーマに撮影中。別冊太陽では『日本書紀』『弘法大師の世界』などの写真を担当。著書に『ショパンの世界へ』(世界文化社)、『おとなの奈良 絶景を旅する』(淡交社)など。写真集に『アイヌの祈り』(求龍堂)がある。
堀内みさ
文筆家。主に日本文化や音楽のジャンルで執筆。近年はさまざまな神社仏閣をめぐり、祭祀や法要、奉納される楽や舞などを取材中。愛猫と暮らす。著書に 『カムイの世界』(新潮社)、『おとなの奈良 心を澄ます旅』(淡交社)、『ショパン紀行』(東京書籍)、『ブラームス「音楽の森へ」』(世界文化社)など。