「南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)」……。
この旅で、何度この言葉を唱えただろう。四国遍路の霊場で、大師像の前で、そして、空海ゆかりの各地の寺で。

「南無」とは、相手に対して敬意を表す際に用いられるサンスクリットの「ナマス(namas)」の音写語で、「大師」は「弘法大師」、「遍照金剛」は、空海が唐で灌頂の儀式を受けた際、師である恵果阿闍梨(けいかあじゃり)から授かった灌頂名であり、大日如来の別名ともされている。なぜなら、「遍照」は太陽の光や月、星の明るさのように、宇宙を遍(あまね)く照らすことで、「金剛」は、金属中でもっとも硬い宝石、つまりダイヤモンドを表し、不滅を意味するからだという。

空海は灌頂を受けた際、目隠しをして曼荼羅の仏たちに華を投げる投華得仏(とうけとくぶつ)という儀式を行ったところ、胎蔵、金剛界ともに、中央の大日如来の上に華が落ちた。


つまり、胎蔵曼荼羅に描かれた414尊、金剛界曼荼羅の1461尊もの仏たちの中で、密教の教主である大日如来と縁を結んだことから、「遍照金剛」の名を授かったのである。
「南無大師遍照金剛」。そう唱えるごとに空海の存在は身近になり、一方で、相反するように人物像のスケール感が増し、巨大になっていったのは、言葉そのものに、空海だけでなく大日如来、ひいては宇宙を称える意味が含まれているからなのかもしれない。いつしか呼び名も「空海」から「お大師さん」、さらに「お大師様」へ。理屈を超えた畏敬の念が、心に、身体に刻まれた。

思えば、「南無大師遍照金剛」という言葉の重みをとりわけ強く感じたのは、平成27年(2015)、高野山の開創1200年記念大法会でのことだった。真言宗という宗派を超え、曹洞宗の永平寺や金峯山修験本宗の金峯山寺などが、法会や柴灯(さいとう)護摩などを行うなか、比叡山延暦寺も法会を行い、最後に職衆全員で「南無大師遍照金剛」と唱えたのである。
他宗の存在を認め、その宗祖を讃えるという、かつての最澄にも通じる天台宗の僧侶の姿勢と、空海という存在の大きさが、改めて心にしっかり刻まれた。


空海の生涯には、空白の期間がいくつかある。しかも、数少ない史実にもさまざまな説が存在し、伝承や伝説にいたっては、荒唐無稽と思えるものも少なくない。著作を繙いても、膨大な仏教経典が高い壁となって立ちはだかり、同時に、それらの仏教経典を自在に扱い、引用しながら、独自の論を展開する空海の卓越した能力に驚嘆し、存在がますます巨大になっていく、そんなジレンマに陥ることもたびたびあった。

知れば知るほどわからなくなり、つかめたと思った次の瞬間、すぐにまた見失う。空海に対し漠とした想いを持ち続けるなか、一筋の光となったのは、やはり空海の著作だった。
空海は教えを説く際、自然のありようを喩えにして表現することがある。その中に、自分のような一般人にも、感覚を共有できる言葉が少なからず存在したのである。
たとえば、個人の心が次第に階梯(かいてい)を上昇し、最終的には密教の心に至るプロセスを表現した『秘密曼荼羅十住心論』の略論、『秘蔵宝鑰(ひぞうほうやく)』の第10章には、我々一般人の心の状態が「蓮華のつぼみ」とすれば、仏心は「蓮華が花開いたよう」であり、我々の身体が「雲に覆われた月」とすれば、仏心は「欠けるところのない満月がくっきりと明るいさまである」と書かれている。


加えて、空海が人生の折々に書いた書簡などを、弟子の真済(しんぜい)が書き写し、10巻にまとめた『性霊集(しょうりょうしゅう)』には、「春には春の花たちが、秋には菊などの秋の花たちが咲いて、私の心を慰めてくれる」など、自然の中に身を置くことの楽しさを親しい友人に書き送っているものもある。




空海の素顔に触れたと感じたのは、そんな時だった。
1200年という時を超え、空海その人と少しでもつながる──それが真実の姿かどうかは別にして──という感覚を持つことができたのは、ひとえに自然という普遍的な存在があるおかげだった。少なくとも、長年森の中で暮らし、木々や動植物、さらに、月や星を身近に感じてきた自分たち夫婦にとって、自然のありようは、空海という人物の一端を理解しようとするうえで必要不可欠な存在だった。





今、改めてこの旅を振り返っても、さまざまな自然の風景が浮かんでくる。
空海の誕生の地と伝わる善通寺近辺の瀬戸内の穏やかな海、

若き日に山林修行をした大峯の山々や石鎚山、



そして、「谷 響きを惜しまず 明星 来影す」という強烈な体験をした、室戸岬近辺の荒々しい岩や風。

さらに虚空蔵求聞持法(こくうぞうぐもんじほう)を修法した大龍嶽では、少しずつ白んでいく空と大地を前にして、バッハの楽曲が浮かんだこともあった。

「平均律クラヴィーア曲集」。自由な書法によるプレリュードと厳格な構成のフーガが、オクターブ内の12の音階すべてにおいて長調と短調で作られ、ハ長調から、長調、短調と交互しながら半音ずつ上がっていく、この24曲から成る曲集は、宇宙という秩序ある世界を音によって表した、いわば小宇宙のような作品である。

なかでもハ長調のプレリュードは、シンプルながら調和した世界観を持つという点において、眼前の風景と同じような宇宙を感じさせた。
日本人として生まれながら、この国で西洋至上主義の教育を受けてきた自分にとって、日本の文化や風土は、幼い頃から慣れ親しんできた西洋音楽や文化のフィルターを通して、その意味や意義を解釈し直すという、なんとも不可思議な状態に陥っている。ある意味この旅は、空海を通して、日本の風土に根ざしたさまざまな祈りの姿に触れ、土地ごとに重層的に積み重なっている信仰というものを、自分の言葉で考えるための時間だったとも言える。











その一方、さまざまな人たちの日々の祈りに触れ、その話に耳を傾けた時間でもあった。


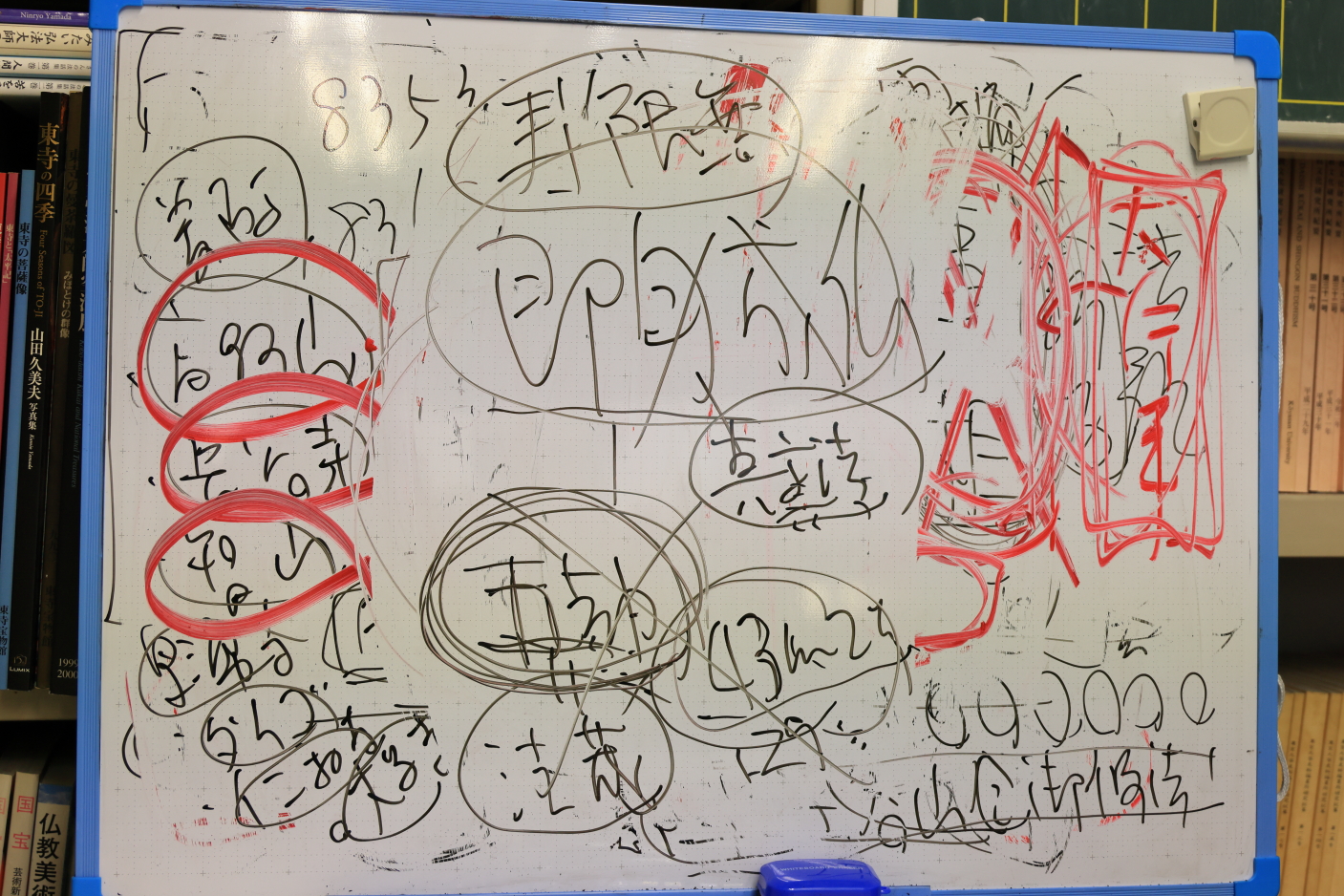


空海の生涯は、いまだにわからないことが多いのも事実である。だが、長い旅を経て、これだけは真実ではないかと思えるようになったことがある。それは、空海が心から人々を救い、その幸せを真剣に願っていた、ということだ。『綜芸種智院の式 并(ならびに)序』や、『高野山万燈会の願文』……。空海の著作を読むたび、その想いは強くなる。

空海の入定後、86年目にあたる延喜21年(921)に、醍醐天皇から下賜された「弘法大師」という諡号(しごう)も、一説では、空海の著作に登場する「弘法利人(りにん)」、つまり「法(密教の教え)を弘め、人々を利益(りやく=仏法の威力によって恩恵を与えること)し救済すること」という言葉が出典ではないかと言われている。
空海が弘仁6年(815)、42歳のときに書いた「勧縁疏(かんえんのしょ)」にも、この「弘法利人」という言葉が登場する。当時、空海は唐から帰国して10年。ようやく密教の普及と定着のために本格的に動き出し、関東や東北地方に弟子を出向かせて、その地の僧侶たちに、唐から請来した密教経典の書写を願い出た。その際、経典の目録とともに添えられたのが、経典書写の趣意書となる「勧縁疏」で、その中に「弘法利人を切に願っている」という言葉があるのだ。

空海の遺志は、1200年以上が経った今も、脈々と受け継がれている。
令和6年(2024)も年明け早々に後七日御修法(ごしちにちみしほ)が厳修され、国家の安泰と国民の幸せが祈られた。

今回導師を務めたのは、この連載でもお話をうかがった善通寺法主(ほっす)の菅智潤(すがちじゅん)さん。法会を終えたばかりの菅法主に、その心境を尋ねてみた。

「真言を唱え、拝んでいると無心になります。集中すると要らない知恵も入ってきません。そういう状態からお堂を出ると、冷静に、次にどのような行動をしたらいいかが浮かんでくる、というのでしょうか。お大師様ご自身も、高野山に行かれていろいろな法要をしっかり行い、拝んでいます。と同時に、すべての人たちを幸せに導く活動を生涯されていました。ですから、拝むと利他はセットなのです」
今後は、元旦に起きた能登半島地震を受け、少しでも温暖化を食い止めるような活動をしていかなければという想いを、いっそう強く抱いていると言う。

現在、さまざまな環境問題が日々の暮らしに影響を及ぼしている。
改めて、空海の言葉を思い返す。
「鳥の声も、それを聞く私の心も、
流れる雲も逝(い)く水も、すべては大日如来の三密(身・口・意)のあらわれ」
早朝の山中の深い静寂の中で修禅に励む自身の心境を、そう表現している。
自然をあるがままに見て、主観と客観という垣根を取り払って一体となる。空海が伝えたかった、悟りにつながる即身成仏の世界は、自然が存在してこそ実現する。その根源が、今ぐらついてきている。
今後も自然への感謝の祈りが失われないように。そして、古来脈々と受け継がれてきた、この国の風土や文化が途絶えないように。
この旅を通し、空海からそんなメッセージを受け取った気がしている。

堀内昭彦
写真家。ヨーロッパの風景から日本文化まで幅広く撮影。現在は祈りの場、祈りの道をテーマに撮影中。別冊太陽では『日本書紀』『弘法大師の世界』などの写真を担当。著書に『ショパンの世界へ』(世界文化社)、『おとなの奈良 絶景を旅する』(淡交社)など。写真集に『アイヌの祈り』(求龍堂)がある。
堀内みさ
文筆家。主に日本文化や音楽のジャンルで執筆。近年はさまざまな神社仏閣をめぐり、祭祀や法要、奉納される楽や舞などを取材中。愛猫と暮らす。著書に 『カムイの世界』(新潮社)、『おとなの奈良 心を澄ます旅』(淡交社)、『ショパン紀行』(東京書籍)、『ブラームス「音楽の森へ」』(世界文化社)など。





