1989年にオープンしたBunkamuraにとって、他にはない複合文化施設としての広がりを象徴するものがオペラであった。しかし、オペラは音楽のみならず演劇、文学、美術、舞踊などあらゆるジャンルを総合した最大級の芸術である以上、上演までに膨大な労力と予算と時間を必要とする。
そんなオペラ上演にまつわるさまざまな困難を解決するための一つの解、それが「コンチェルタンテ」である。いわゆる演奏会形式上演のことであるが、そこから一歩踏み出して、手の込んだ贅沢な舞台装置など使わなくとも最小限の演出さえあれば、演劇的にも十分に満足いくものとして、さまざまなオペラの演目を上演できる――。そんな新たな可能性が、Bunkamuraオーチャードホールから生み出されていった。
大野和士と仲間たちによる「東京フィル オペラコンチェルタンテ・シリーズ」

1990年代におけるBunkamuraオーチャードホールのイメージを決定づけた重要なシリーズの一つが、東京フィルハーモニー交響楽団の主催による「オペラコンチェルタンテ・シリーズ」。第1回(1992年5月11日)をバーンスタイン《ウエストサイド・ストーリー》で開始し、第23回(2002年2月8日)をブゾーニ《ファウスト博士》(日本初演)で終えるまでの10年間で、ダブル・ビルやトリプル・ビルを数え入れると合計28演目ものオペラ作品が上演されている。

そのほとんどは当時常任指揮者をつとめていた大野和士の指揮によるもので、イタリア・オペラの名作(それとて従来上演回数の少ないものもあった)のみならず、通常のオペラ公演では実現の難しい、しかし音楽史的にみると重要な演目も多く含まれていた。いくつか例を挙げてみる。
第2回:サリエリ《音楽が第一、言葉は次に》&ツェムリンスキー《フィレンツェの悲劇》(日本初演)
第5回:プロコフィエフ《炎の天使》(日本初演)
第9回:ショスタコーヴィチ《ムツェンスクのマクベス夫人》(ロシア語日本初演)
第11回:ヒンデミット《殺人者・女たちの希望》《聖スザンナ》《ヌシュ-ヌシ》(すべて日本初演)
第13回:ブリテン《ピーター・グライムズ》
第15回:ヤナーチェク《イェヌーファ》(チェコ語日本初演)
第17回:R.シュトラウス《無口な女》(日本初演)
第19回:シュレーカー《はるかなる響き》(日本初演)
新国立劇場は1997年秋のオープンだが、それよりも前から東京フィルの「オペラコンチェルタンテ・シリーズ」は、従来の二期会や藤原歌劇団、あるいは来日オペラ団体がなかなか上演できなかった、とりわけ20世紀のオペラの名作を1990年代にいち早く手掛けてきたのである。その功績は大きい。
公演プログラム冊子を見ると、最初の5回分と第11回(ヒンデミット:3部作)には、台本の原語と対訳が全文掲載されており(これは今では滅多に見られない)、音楽のみならず言葉への制作チームの熱い思いが伝わってくる。主催者側にとっては過大な労力かもしれないが、観客が鑑賞後にオペラを音楽だけでなく演劇としても振り返りたいときに、台本を上演側による責任を持った日本語としてじっくり読めるように便宜が図られていることは、とても大切なことである。演目が珍しければなおさらのことだ。
第1回の《ウエストサイド・ストーリー》のプログラム冊子には、大野和士自身による長文の解説が掲載されている。それは、かつてタングルウッド音楽祭で教えを受けたバーンスタインへの強い敬愛の念を書いた内容であるとともに、「オペラコンチェルタンテ・シリーズ」を貫く一種のマニフェストとして読むことも可能である。そこには、自然で臨場感あふれる原語の響き、質の高い歌唱(と舞踊)、作品の持つ社会的背景を深く考察すること――への強いこだわりが表明されていた。
当時の取材を通じてよく覚えているが、「オペラコンチェルタンテ・シリーズ」は、大野和士を中心としながらも、緑川まりをはじめとする多彩で強力な歌手陣、初回から最終回まで構成を手掛けた大橋マリやコレペティートルの足立桃子を中心とした制作チーム全体の知恵と献身の賜物であった。演目によっては、専門家や音楽学者たちの協力も仰ぎながら、未知のオペラにも体当たりでぶつかっていく冒険心と熱気は、演奏を通じて客席にいる側にも伝わってきた。オペラ指揮者大野和士にとっての、欠かすことのできない原点の一つが「オペラコンチェルタンテ・シリーズ」だったはずである。オーケストラにとっても、“オペラの東京フィル”という評価をさらに高めたのは、このシリーズあればこそであった。
個人的に印象に残っているのは、第5回(1993年6月9日)のプロコフィエフ《炎の天使》と、第9回(1994年11月26日)のショスタコーヴィチ《ムツェンスクのマクベス夫人》という、二つの重要なロシア・オペラが取り上げられたことである。どちらも危険でエロティックな場面を含むセンセーショナルな作品でもあった。当時はソ連共産党の崩壊にともない、鉄のカーテンの向こうから一挙にさまざまな情報が流出し、ロシア音楽の研究にも大きな前進が見られた時期である。ロシア音楽学者・一柳富美子が公演スタッフに加わったことで、最新の研究成果の反映されたダイナミックな上演の場になっていったことも忘れがたい。
コンサートホールや劇場にとって、自主制作公演は最も重要だが、貸館公演であっても、それが長期にわたる企画であるならば、その意味合いは大きなものとなる。東京フィルの「オペラコンチェルタンテ・シリーズ」の会場であった1990年代のBunkamuraオーチャードホールは、いま一番面白い、冒険的なオペラのシリーズが聴ける場として、どれほど観客をわくわくさせてくれたことだろう。
大野和士とBunkamuraの密接な関係の証しでもあった、フランス国立リヨン歌劇場とベルギー王立歌劇場(モネ劇場)の来日公演
2009年8月18日。大野和士はBunkamuraオーチャードホール・ビュッフェでおこなわれた記者懇親会の席上、自らが首席指揮者をつとめるフランス国立リヨン歌劇場の来日公演「ウェルテル」(演奏会形式上演)を11月に控えて、「オペラコンチェルタンテ・シリーズが戻ってくると思ってほしい」と述べた。これは大野自身がどれほどこのシリーズを愛していたかの裏返しでもあったし、まだ今後も「コンチェルタンテ」というオペラ上演の形式に可能性があると考えていた証しでもあった。
実はBunkamura主催によるフランス国立リヨン歌劇場の来日公演はこれが初めてではなく、1997年9月《カルメン》(演奏会形式、ケント・ナガノ指揮、アンネ=ゾフィー・フォン・オッター主演)が初来日であった。当時人気絶頂だったメゾソプラノのフォン・オッターがカルメンに初挑戦するということで話題となったこの公演は、他のキャストがいわゆる「演奏会」スタイルの歌唱にとどまっていた一方で、フォン・オッターだけが孤軍奮闘の演技入りの熱唱で、そのばらつき感がやや残念な印象を残した。やはりコンチェルタンテが成功するには全員のチームプレイが欠かせないのだ。
当時のフランス国立リヨン歌劇場は、辣腕プロデューサーのジャン=ピエール・ブロスマンが率いており、演劇的にも洗練された現代的なオペラ劇場として世界中の注目を浴びる存在であった。老舗ブランドとして確立された有名な歌劇場ではなく、一般的な知名度はなくとも、いま本当に面白い歌劇場や音楽祭を呼んでくるBunkamuraが、フランス国立リヨン歌劇場の来日公演を主催するのは当然の流れだった。だが初来日の《カルメン》は彼らの個性が十分に発揮された公演とは言い難かった。
その12年後となる2009年11月の再来日は、首席指揮者に就任した大野和士の凱旋公演でもあった。何よりも、大野自身が「コンチェルタンテの再来」と自負するだけの内容があった。一人のスター歌手だけが突出することなく、全員がチーム一丸となって、舞台装置はなくとも十分にオペラと言い切れるだけの演劇性が歌手たちの歌と身振りから伝わってきた。

まだ十分に親しまれているとは言い難いフランスの作曲家マスネのオペラ《ウェルテル》について大野は、「フランスの《トリスタンとイゾルデ》だと思ってほしい」と述べた。ドイツの文豪ゲーテの原作でありながら、フランス人にしか書けない究極の愛のドラマ。エレガントな響きを持つリヨンの劇場専属オーケストラをバックにウェルテル役のジェイムズ・ヴァレンティが歌う、有名なアリア「春風よ、なぜ私を目覚めさせるのか」の暗く不吉に、生暖かくうねるような音楽は、いまも耳にこびりついている。
この上演の成功を受ける形で、さらにその5年後の2014年7月には、再びフランス国立リヨン歌劇場が来日し、Bunkamura主催によるオッフェンバックの名作《ホフマン物語》(大野和士指揮、ロラン・ペリー演出・衣装)の完全舞台上演が実現した。ロラン・ペリーはいまフランスで最も活躍する演劇的なセンスにあふれた演出家の一人だが、彼がこのときに取材に答えて語った以下の言葉は、そのままコンチェルタンテの精神にも応用できるものだ。

「一番重要なのは、音楽と歌手です。演出は音楽の一部でなければならない」
《ホフマン物語》は詩人ホフマンが恋した3人の女性(オランピア、アントニア、ジュリエッタ)とそれを総合したヒロインのステッラをめぐる物語だが、この上演ではこの4役をパトリツィア・チョーフィ一人が演じた。ペリーの演出は最小限の舞台装置を生かしつつ、このオペラに潜む暗く魔術的な面を強調するものであった。大野指揮のリヨン歌劇場のオーケストラは、決してシンフォニックに吠えたりせず、歌を完璧に支え、密度の濃い音楽を展開した。たとえば魔術師ダペルトゥットが娼婦ジュリエッタを籠絡するダイヤモンドの輝きについて歌っているとき、オケはそのダイヤを包み込む薄絹のような、うっとりと香るような音を奏でていた。これは他のオケではなかなか聴けない美学だと感じた。
紹介する順序が逆になったが、フランス国立リヨン歌劇場の前に大野和士が首席指揮者をつとめていたベルギー王立歌劇場(モネ劇場)の来日公演でモーツァルト《ドン・ジョヴァンニ》(デイヴィッド・マクヴィカー演出)が2005年10月にBunkamura主催によりオーチャードホールで実現していたことにも触れておきたい。
これも、「オペラコンチェルタンテ・シリーズ」をきっかけとして大野とBunkamuraの間に結ばれた深い関係の表れである。
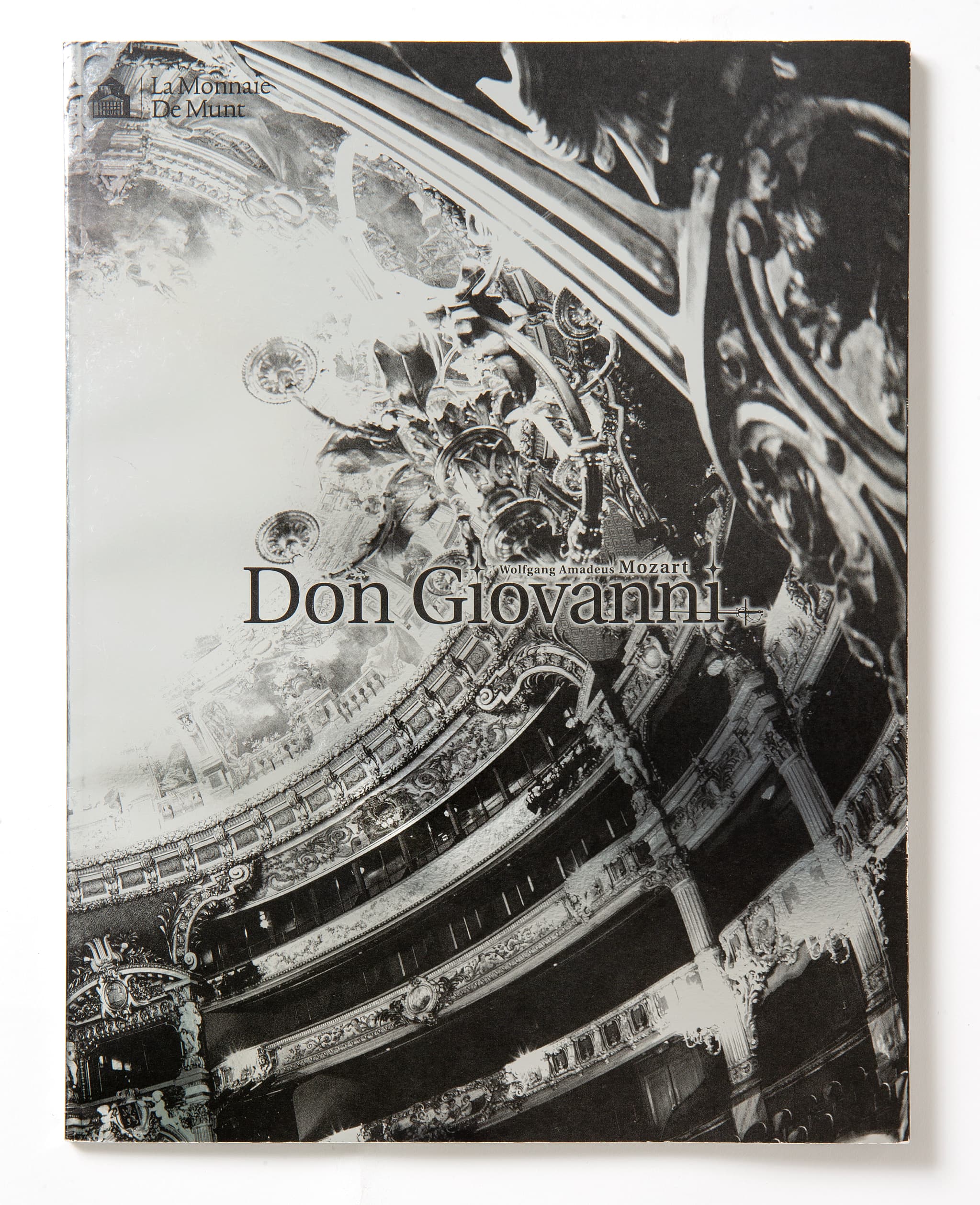
ベルギーの首都ブリュッセルのモネ劇場は、フランス語圏とドイツ語圏の文化の架け橋であり、ヨーロッパの劇場シーンにおける新しいムーブメントの震源地として、常に注目されてきた(かつて振付家モーリス・ベジャールが二十世紀バレエ団とともに1960年頃から20数年にわたり活動していた本拠地であり、のちにアンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルがモダン・ダンス・カンパニー「ローザス」の拠点とした場所でもある)。
来日当時の総監督はベルナール・フォックロー。世界屈指のオルガニストとしてバッハ作品全集を録音する一方で、バロック・オペラや現代オペラにも詳しかった。のちにはエクサンプロヴァンス国際音楽祭の芸術監督に転出し、さらに大野のキャリアを支える存在となっていく重要人物である。
このときの《ドン・ジョヴァンニ》のマクヴィカーの演出は、モーツァルトの音楽の中の陰鬱な夜の世界を美しく描き出すものだったが、たとえばラストシーン近くの地獄落ちの場面では、騎士長の姿は墓場から蘇ったゾンビのように恐ろしいものであった。死の恐怖がロマンティックな音楽と響き合うこの舞台は、モーツァルトの音楽をより雄弁なものとして体験させてくれた。
なお、このモネ劇場の来日公演では、ソニー音楽財団の主催で「子どもたちに贈るオペラ《ドン・ジョヴァンニ》」がBunkamuraオーチャードホールで上演されている。イタリア語の上演で字幕なしだが、大野が物語や登場人物について子どもたちが楽しめるよう解説を付けるという趣向だった。モネ劇場が日頃から力を入れている教育プログラムのアウトリーチもこの機会におこなわれた。
オペラが単なる贅沢な芸術というだけではない、人間が成長していく上で重要な役割を果たしうる文化であり、社会に幅広く共有されるべきだというビジョンが示されたという意味でも、これは記憶に残る来日であった。
再びコンチェルタンテの時代が来る
それは、再び《ウエスト・サイド・ストーリー》から始まった。
バーンスタイン生誕100周年の記念イヤーを機に、Bunkamuraはパーヴォ・ヤルヴィ&N響《ウエスト・サイド・ストーリー》演奏会形式・シンフォニー・コンサート版を上演した(2018年3月4、6日オーチャードホール)。
実はBunkamuraオーチャードホールは、レナード・バーンスタインが亡くなる直前に来日した1990年夏、ロンドン交響楽団を指揮しての最後の公演(7月12日)がおこなわれた場所でもある。一方、パーヴォ・ヤルヴィは、主にシンフォニー指揮者として卓越した成果を上げてきた人だが、バーンスタインから直接教えを受けた体験をとても大切にしていた。晩年のバーンスタインがミュージカル的な舞台作品《キャンディード》を演奏会形式で登場人物をあまり動かさずにただ歌うだけのバージョンで上演したことをとても気に入っていたことから、今回の《ウエスト・サイド・ストーリー》シンフォニー・コンサート版での上演につながったという。
セリフを最小限にカットし、ダンスもなしという上演形態は、ある意味大きな冒険であるが、それだけに名曲「サムウェア」をピークとする音楽の途方もない美しさを、マリア役のジュリア・ブロック、トニー役のライアン・シルヴァーマンらアメリカから招聘された主要歌手陣の歌と、N響の演奏とともにライブで味わう喜びがあった。
「あらゆる分断、差別、暴力を乗り越えて、平和と自由の大切さを訴える」と言葉にしてしまうと、いかにも当たり前すぎる理想主義的スローガンに思えてしまうかもしれないが、それが音楽の魔法によって、恐るべきリアリティをもって誰の心にも響いてくるのが、《ウエスト・サイド・ストーリー》の偉大さでもある。
次にパーヴォ・ヤルヴィがN響との演奏会形式上演の演目に選んだのが、ベートーヴェン唯一のオペラ《フィデリオ》(2019年8月29日、9月1日オーチャードホール)。「第九」交響曲にも通じる、自由と博愛と民主主義をテーマとするこの作品は、近年ドイツの劇場でしばしば見られる“現代的”な演出によって、屈折した解釈で舞台化されることが多い。そうした中、ヴォルフガング・コッホ(ドン・ピツァロ)、ミヒャエル・シャーデ(フロレスタン)、アドリアンヌ・ピエチョンカ(レオノーレ)、フランツ=ヨーゼフ・ゼーリッヒ(ロッコ)、モイツァ・エルトマン(マルツェリーネ)ら超一流キャストを集め、ドイツものを得意とするN響が本領を発揮したこの上演は、改めて音楽面からこのオペラの魅力の根源を見つめ直す良い機会となった。次のパーヴォ&N響の第3弾として予定されていた《カルメン》がコロナ禍によって中止されたのは残念であった。

© 堀衛
「オペラコンチェルタンテ」のDNAは、東京二期会の制作・主催でBunkamuraが共催しオーチャードホールで上演する「東京二期会コンチェルタンテ・シリーズ」にも継承された。オーケストラを囲むように設置されたステージで、映像と照明を効果的に用いるセミ・ステージ形式のオペラ上演である。2018年のベッリーニ《ノルマ》に始まり、マスネ《エロディアード》、サン=サーンス《サムソンとデリラ》、プッチーニ《エドガール》、そしてR.シュトラウス《平和の日》(日本初演)と意欲的な演目が続いた。なかでも個人的に強い印象を受けたのは、フランスの老巨匠ミシェル・プラッソンが東京フィルを指揮した《エロディアード》(2019年4月27、28日)である。甘い旋律の中に憧れの要素が秘められたマスネの音楽の魅力を、節度ある演奏によって堪能した。やはりコンチェルタンテ形式の場合、指揮者の存在はとても大きいのだ。
2022年秋には、新たなBunkamura自主制作として、「Bunkamuraシアター・オペラ・コンチェルタンテ」でヴェルディ《椿姫》(10月7、10日オーチャードホール)が上演された。森麻季(ヴィオレッタ)、山本耕平(アルフレード)、大西宇宙(ジェルモン)、林美智子(フローラ)ら、舞台感覚に優れた強力な日本人キャストが組まれ、椅子などの最小限の装置が巧く生かされて、演劇的にも洗練された上演となった。東京フィルを率いたウィーン国立歌劇場出身の指揮者サッシャ・ゲッツェルの手腕も際立っていた。華道家・假屋崎省吾が舞台と会場の装花を担当したことは、オペラの余韻をいっそう味わい深いものにしていた。
実はこの《椿姫》の半年前に、ゲッツェルと1時間ほど話をする機会があった。そのときに彼はこんなことを言っていた。
「コンチェルタンテでオペラを上演する場合には、どんな感情を持って歌い演じるべきかという、その“スペース”を歌手に与えなければいけない。たとえば愛し合う二人をソプラノとテノールが演じるときには、お互いをどのように愛しているのか、それは本当の愛なのか、それとも条件付きの愛なのか、シチュエーションをちゃんと考えて歌ってくださいと言います。そうすることで本当に彼らの声が変わるのです」
本稿では、これまでBunkamuraオーチャードホールで、いかに多くのオペラが「コンチェルタンテ」形式で上演されてきたかを振り返ってきた。そこには、新しい演目を次々と上演できるフットワークの良さというメリットもあったし、スタンダードな演目であっても、音楽や台本に改めて向き合うことでハイ・レべルな演奏の場にもなりうるというメリットもあった。大がかりな舞台装置がなくとも、ちょっとした工夫で見事な演劇的効果を生み出す例もあった。今後も、優れた指揮者を中心に、歌手もスタッフも一体となって、良いチームワークが成立するならば、「オペラコンチェルタンテ」には無限の可能性があるに違いない。








