第二十九帖 行幸
<あらすじ>
十二月、大原野へ帝の行幸(みゆき)がありました。華やかな行列を見ようと人々が集まり、六条院の女性たちも牛車を連ねて出かけます。行幸の列は親王をはじめとして、源氏を除いた公卿たち文武百官うちそろい、殿上人(てんじょうびと)から五位六位に至るまで、晴の青色の袍に葡萄染の下襲(したがさね)を着ていました。
玉鬘は帝は源氏と似ているけれども、もっと崇高で上品だと思います。その素晴らしい美しさを見た後に実父の内大臣を見ますと、やはり劣って見えてしまうのです。武装した右大将は色黒で髭が多く好感が持てません。最近、源氏に宮仕えを勧められていましたが、「あの帝のお側にお仕えするのなら素敵かもしれない」と思うのでした。源氏の狙いはまさにそこだったのです。
玉鬘の裳着(もぎ)の腰結(こしゆい)役を内大臣に依頼すると「大宮(内大臣の母)の体調が悪いので」と断ってきましたので、源氏は三条宮の大宮を見舞います。重病ではなかった大宮は「(孫の)源氏の中将が良くしてくれるので長生きできます」と語ります。やがて源氏が「尚侍として宮仕えさせようと思った娘が内大臣の子であると判りました」と切り出すと大宮は驚き、息子の内大臣を呼び出します。内大臣は源氏の中将と我が娘、雲居雁の姫についての話かと思い、三条宮に向かいました。
久しぶりに内大臣と面会した源氏が、引き取った玉鬘が内大臣の子であることを打ち明けると内大臣は大いに驚き、喜びます。二人はすっかり昔に戻って仲良く話を続けました。そして内大臣は玉鬘の腰結役を承諾。裳着の儀式はさまざまな方面から豪華な贈り物が届く盛大なものとなりました。
律儀に儀式を重んずる末摘花からも御祝いが届きますが、これがまったく古くさい装束です。例によって古風な「唐衣」にちなんだ歌も添えられていましたので、源氏は呆れて「唐衣また唐衣唐衣 かへすがへすも唐衣なる」という戯れ歌を返すのでした。
内大臣の今姫君・近江の君は、自分と同じ庶民出身の玉鬘がちやほやされているのを聞いて大いに羨み、弘徽殿女御に「私も尚侍にしてください」などと、とんでもないことを言い出すのです。父・内大臣にも直訴しますが、内大臣は「辛いときは近江の君を見ると気が紛れるな」と苦笑するばかりなのでした。

<原文>
「その師走に、大原野の行幸とて、世に残る人なく見騒ぐを、六条院よりも、御方々引き出でつつ見たまふ。(中略)今日は親王たち、上達部も、皆心ことに、御馬鞍をととのへ、随身、馬副の容貌丈だち、装束を飾りたまうつつ、めづらかにをかし。左右大臣、内大臣、納言より下はた、まして残らず仕うまつりたまへり。 青色の袍、葡萄染の下襲を、殿上人、五位六位まで着たり。」
<現代語訳>
(この十二月に洛西の大原野の行幸があって、だれも皆お行列の見物に出た。六条院からも夫人がたが車で拝見に行った。(中略)今日は親王がた、高官たちも皆特別に馬鞍を整えて、随身、馬副男(うまぞいおとこ)の背丈までもよりそろえ、装束に風流を尽くさせてあった。左右の大臣、内大臣、納言以下はことごとく供奉したのである。浅葱(あさぎ)の色の袍に紅紫の下襲を殿上役人以下五位六位までも着ていた。 )
大原野は洛西に位置し、その中心地にある大原野神社(京都市西京区大原野南春日町)は藤原氏出身の皇后が春日大社の代わりに参詣する氏神様として知られています。
ここは古来たびたび帝の野行幸が行われた地で、「野行幸」というのは帝が鷹狩りを見る行幸です。平安京を開いた桓武天皇は鷹狩りを好み、延暦十五年(七九六)に「主鷹司(しゅようし)」という役所を設置し、たびたび遊猟に出た記録が『日本後紀』に見られます。また『吏部王記(りほうおうき)』によれば延長六年(九二八)十二月、帝が赤色袍を着用し鳳輦(ほうれん)に乗って大原野行幸をしたとあります。『源氏物語』の記述は、この『吏部王記』に基づく描写がなされているのです。
行幸は、人々が帝をはじめとする高貴な人々を目にすることができる貴重な機会でしたので、数多くの見物人が繰り出しましたし、見られる側の廷臣たちも特に美しく着飾りました。ここでは源氏以外の文武百官がうちそろって青色袍を着用し、帝に供奉しています。「青色」は宮廷における最高のお洒落な色とされ、人々の耳目を集める特別な場合に着用されました。「青白橡」と同じ色彩とされ、『延喜式』(縫殿)によれば黄色の「苅安草」と紫色の「紫草」で染める複雑な色調のダークグリーンでした。
<文献>
『新儀式』
「野行幸事 若有野行幸、冬節行之。預定其程、令仰上卿可有行幸之由、即令勘申吉日。又尋常鷂飼鷹飼等之外、若有知猟道親王公卿并非参議四位五位、令仰可供奉鷂飼鷹飼之由、又奉仰上卿参議率装束使弁少将史等向可幸野、点定御在所及可立諸司幄所々。」
『日本後紀』
「延暦十一年(七九二)二月癸卯《十八》。遊猟于大原野。延暦十二年(七九三)九月癸未《七》。遊猟于大原野。延暦十三年(七九四)十二月丙辰《十七》。遊猟於大原野。」
『吏部王記』(重明親王)
「延長六年十二月五日。大原野行幸。卯初上御輿。自朱雀門至五条路西折。到桂河辺。上降輿就幄。群臣下馬。上御輿。群臣乗馬渡〔浮〕橋。〈方舟。其上為輿敷板。〉自桂路入野口。鷹飼到此持鷹。員外鷹飼祗候。武官著青摺衣者四人。摺衣徒伺所扈従也。鷹飼親王公卿立本列。其装束御赤色袍。親王公卿及殿上侍臣六位以上著麹塵袍。」
『河海抄』(四辻善成)
「仁和二年十二月十四日戊午寅四剋行幸芹河野為用鷹鶴也。李部王記云延長六年十二月五日大原野行幸卯初上御輿。」
『延喜式』(縫殿)
「青白橡 綾一疋<綿紬・糸紬・東絁亦同>。苅安草大九十六斤。紫草六斤。灰三石。薪八百四十斤。」


大臣大饗の鷹飼 『年中行事絵巻』(国立国会図書館デジタルコレクション)
〈原文〉
「親王たち、上達部なども、鷹にかかづらひたまへるは、めづらしき狩の御よそひどもをまうけたまふ。近衛の鷹飼どもは、まして世に目馴れぬ摺衣を乱れ着つつ、けしきことなり。」
〈現代語訳〉
(親王がた、高官たちも鷹使いのたしなみのある人は、野に出てからの用にきれいな狩衣を用意していた。左右の近衛、左右の衛門、左右の兵衛に属した鷹匠たちは大柄な、目だつ摺衣(すりごろも)を着ていた。)
飼いならした鷹を放って雉や小鳥などを狩猟する「鷹狩」は中央アジアが起源とも言われ、日本でも埴輪に鷹匠が見られるように古代から好まれました。嵯峨天皇は『新修鷹経(しんしゅうようきょう)』という放鷹術書を編纂させています。鷹狩には冬の「大鷹狩」と秋の「小鷹狩」があり、前者はオオタカ(大鷹、学名:Accipiter gentilis)、後者はハイタカ(鷂、学名:Accipiter nisus)が主に使われました。『西宮記』では「大鷹の鷹飼は地摺の狩衣を着、鷂の鷹飼は青摺白橡の袍を着る」と区別されています。
神事でも用いる「青摺」の衣類は禁色(きんじき)扱いで着用が厳しく制限されていました。ただし天長二年(八二五)二月、諸衛府の鷹飼官人は行幸で鷹を据えて供奉するときに「摺衣」を着用することが許されたと『政事要略』に記されています。『源氏物語』で「世に目馴れぬ 摺衣」というのはそれを指しているのです。そして鷹飼たちが「錦帽子」と呼ばれる風変わりな頭巾を被りました。
また「狩衣」は本来狩猟用なので親王や高位の公卿もここで着用しますが、これが「めづらしき狩の御よそひ」であったのです。
<文献>
『政事要略』
「或云。鷹飼着摺衣袴。御馬乗近衛又号調袴着用摺袴。禁制之外。古来之例也者。今此鷹飼馬乗之類。未見着用摺衣之由。天長二年二月四日宣旨云。一聴鷹飼官人着摺衣事。右左大臣宣。奉勅。諸衛府鷹飼官人。行幸之時。執鷹供奉。聴着摺衣。又類聚部仁和二年九月十七日宣旨云。鷹所鷹飼四烈。右近衛将曹坂上安生云々。已上四人許摺衣緋鞦。左兵衛権佐藤原朝臣恒興云々。已上三人許摺衣。左近衛日下部安人已上一人。許不帯弓箭。鷂飼四烈。右兵衛権少志布勢春岡云々。已上四人許摺衣并緋鞦。蔭子菅原冬緑云云。已上七人許摺衣。左近衛下毛野松風云々。已上四人許不帯弓箭。中納言従三位藤原朝臣山蔭宣。奉勅。件等人応免摺衣緋鞦并兵仗不具之責。又延長四年十一月四日宣旨云。右馬頭源朝臣云々。已上四人鷂飼。聴着摺衣袴。近江大掾御春朝臣望晴云々。已上四人鷹飼。聴着摺衣。左大臣宣。奉勅。明日可有北野行幸。件等人摺衣宜聴禁止。但毎野行幸。立為永例者。自余之例。具見類聚。依野行幸。有別宣旨。御鷹飼等聴摺衣例御鷂飼皆在此中。依斯案之。尋常難着。又検式。御馬乗近衛不聴着摺袴。衛府之輩牢籠自着歟。為披昏蒙。聊以記註。或人云。邑上天皇御代。藤原季平為蔵人式部丞。新甞会着青摺立列不可然。式部答云。為蔵人輩。被聴雑袍。不存其旨。所教正不可然。時人聞云。省台所謂遥以有興焉。始自此時。蔵人式部丞。着小忌装束立本列云々。誠雖口伝之説。可知濫觴之時。」
『醍醐天皇御記』
「延喜十八年十月十九日。幸北野。(中略)鷂鷹鷹飼兼茂朝臣。伊衡。言行。以上青麹塵雲雁画褐衣。紅接腰等但並如去年装束。但浅紫布袴、以花摺唐草鳥形。雄鷂々飼源茲。同教。小鷹鷹飼源供。良峯義方。以上四人、檜皮色布褐衣。鷂黄画鳥柳花形。紫村濃布袴。青接腰。帯。紫脛巾。各臂鷹鷂。八人一列。」
『西宮記』 (源高明)
「延長六年十月十八日、貞公記云、中使平頭立門外、御狩事也、鷹飼親王、大納言摺衣、自余麹塵、諸衛府生以上、褐衣、腹纏、行縢、舎人青摺、狩長四人、狩子四十人定了、」
「北野行幸、天皇服白橡御衣、延喜御時、天皇御右近馬場、改着直衣云々、王卿如例、衛府公卿着弓箭又如例、其鷹飼王卿、大鷹々飼者、着地摺猟衣綺袴玉帯、鷂々飼者、青摺白橡袍綺袴玉帯巻纓、皆有下襲、其帯剣之者有尻鞘、但、至于王卿之鷹飼、入野之後、可着行縢餌袋等歟。」
『長秋記』(源師時)
「天永四年正月十六日、太政大臣家大饗、(中略)次御鷹飼渡。(中略)流文狩衣紫裏白、両面袴、紅衣、同色単衣、熊行騰、壺脛巾、浅沓、烏帽子ウヤヲカケリ、其上著錦帽子、又ウヤヲカク、結緒、〈カタカギナリ〉鳥頸劒〈件劒顯季劒也、而上皇賜装束、次借召預給云々、銀作鴛頸切螺鈿劒、無目貫、左手入革嚢、付餌袋、件餌袋具、斑豕尻鞘入劒螺鈿。柴一枝、指雌雉一羽、鈴付尾無鈴〉」


ハイタカ(学名:Accipiter nisus)『蘭山禽譜』(国立国会図書館デジタルコレクション)
〈原文〉
「西の対の姫君も立ち出でたまへり。そこばく挑み尽くしたまへる人の御容貌ありさまを見たまふに、帝の、赤色の御衣たてまつりて、うるはしう動きなき御かたはらめに、なずらひきこゆべき人なし。」
〈現代語訳〉
(六条院の玉鬘の姫君も見物に出ていた。きれいな身なりをして化粧をした朝臣<あそん>たちをたくさん見たが、緋<ひ>のお上着を召した端麗な鳳輦の中の御姿になぞらえることのできるような人はだれもない。
玉鬘に帝の美しい姿を見せて心を動かそうとした源氏。思惑どおりに玉鬘は帝の姿に見ほれ、尚侍としての出仕に前向きな気持ちになります。参加者全員が「青色」の袍を着ている中で、鳳輦に乗る帝だけは「赤色」の御袍を着ている姿が目立ちます。『吏部王記』の延長六年(九二八)の項にも「主上御輿。著赤色袍」と記されています。また『源氏物語』では「少女」の帖にも「人びとみな青色に桜襲(さくらがさね)を着たまふ。帝は赤色の御衣たてまつれり」とあります。
赤色は「赤白橡(あかしろつるばみ)」とも呼ばれる色彩で、青色よりもワンランク上の色とされました。『西宮記』には正月行事「内宴」において帝が赤色、廷臣が青色を着ると記されていますが、あわせて「最上位の臣下も赤色を着る」とあります。『吏部王記』には右大臣が内宴で赤色袍を着て咎められたという記事が見られますが、太政大臣の源氏がもしも行幸に参加していれば、帝と同じ赤色袍を着ていたことでしょう。
「赤白橡」は『延喜式』(縫殿)によれば「黄櫨」(ハゼノキ)と「茜」(アカネ)で染める色彩で、江戸時代の御所調進控の上皇御袍裂地を見ると、赤みの強いレンガ色のような色彩です。
<文献>
『吏部王記』(重明親王)
「延長六年十二月五日。(中略)行幸大原野。御鷹飼逍遥云々。親王公卿及殿上侍臣六位以上著麹塵袍。(中略)主上御輿。著赤色袍。」
『西宮記』 (源高明)
「内宴、天皇御服赤白橡<縫腋、近代闕腋>、皇太子王卿已下、同服麹塵闕腋袍着魚袋靴等。帯剣之者着飾剣。但、文人者文官服縫腋着魚袋靴等。先例、当日上卿或服赤白橡袍。」
『吏部王記』(重明親王)
「天暦元年正月廿三日。内宴。是日右大臣著赤白橡袍。式部卿親王咎之。上代諸卿或雖著之。近年無同御服者。太政大臣時時服。摂政之重異於他人歟。主同服所未安也。」
『延喜式』(縫殿)
「赤白橡 綾一疋<綿紬・糸紬・東絁亦同>。黄櫨大九十斤。灰三石。茜大七斤。薪七百廿斤。」
『延喜式』(弾正)
「凡赤白橡袍。聴参議已上著用。」
『河海抄』(四辻善成)
「延長四年十月十九日大井行幸上服赤色袍黄櫨染御袍文竹鳳臨時祭庭座賭弓射場始或又朝覲行幸後出御等時被用之云々。晴儀ニ諸臣青衣の袍を着する時は主上赤色御袍を着せしめ給也第一座の人又着之是諸臣にことなる色也。」
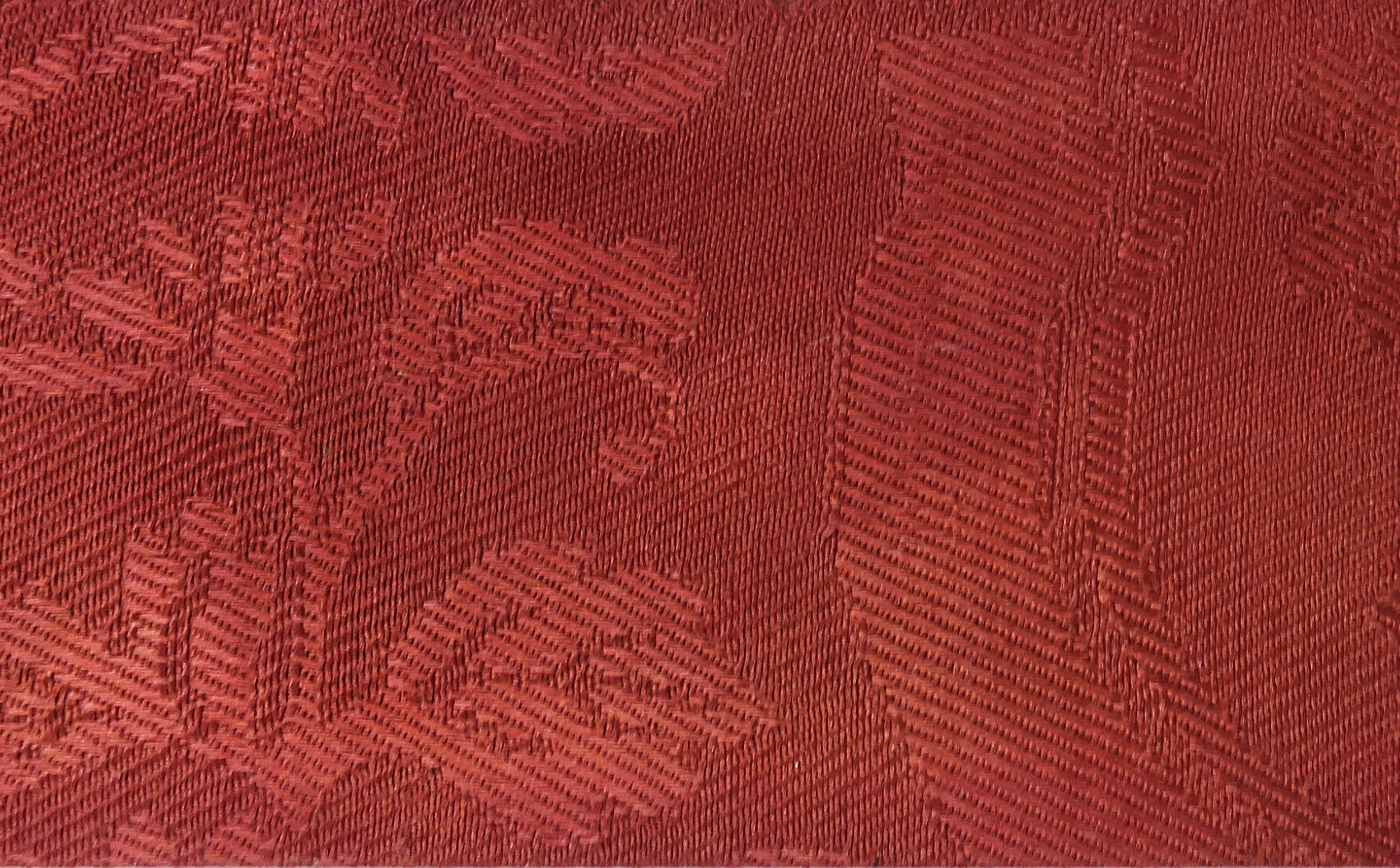

青色袍の公卿と赤色袍の天皇 『年中行事絵巻』(国立国会図書館デジタルコレクション)
〈原文〉
かうて、野におはしまし着きて、御輿とどめ、上達部の平張にもの参り、御装束ども、直衣、狩のよそひなどに改めたまふほどに、六条院より、御酒、御くだものなどたてまつらせたまへり。今日仕うまつりたまふべく、かねて御けしきありけれど、御物忌のよしを奏せさせたまへりけるなりけり。蔵人の左衛門尉を御使にて、雉一枝たてまつらせたまふ。仰せ言には何とかや、さやうの折のことまねぶに、わづらはしくなむ。」
〈現代語訳〉
大原野で鳳輦が停められ、高官たちは天幕の中で食事をしたり、正装を直衣や狩衣に改めたりしているころに、六条院の大臣から酒や菓子の献上品が届いた。源氏にも供奉することを前に仰せられたのであるが、謹慎日であることによって御辞退をしたのである。蔵人の左衛門尉を御使いにして、木の枝に付けた雉子を一羽源氏へ下された。この仰せのお言葉は女である筆者が採録申し上げて誤りでもあってはならないから省く。
「御輿(みこし)」というのは数人で肩上に担ぐ乗り物で、頂上に鳳凰(ほうおう)の飾りがある「鳳輦」は帝専用の乗り物でした。野行幸を詳しく記した『新儀式』には「野御輿というものもあるが尋常御輿を用いるのが通例である」とあり、これは鳳輦のことでしょう。ただし『小右記』によれば「節会と正月三が日の行幸が鳳輦で、臨時行幸は葱花輦(そうかれん)を用いるのだが、最近は旧例によらず鳳輦を用いている」とあります。
現地には「軽幄(けいあく)」と呼ばれるテントを張って帝の御座所とし、ここで猟の獲物を見たり宴を開いたりしました。鷹狩りで獲た鳥は「鷹の鳥」と呼ばれ、さまざまな種類の鳥がありましたが、饗宴で用いられるのは美味な雉に限り、焼き鳥にして食べることが本儀であったようです。『吏部王記』には火炉
(かろ)一具が帝の御膳に運び込まれ、近衛の将監が帝や公卿の食べる雉を調理したと記されています。
源氏が賜った雉が「一枝」というのは、獲物の雉は花のない梅あるいは五葉松の枝に結び付けて運ぶことが定式であったからです。『徒然草』には鎌倉後期の関白・近衛家平が「花の付いた紅梅の枝に二羽付けよ」と命じたところ、鷹飼が「花の枝に鳥を付けること、二羽付けることは聞いたことがありません」と答え、枝の長さは六~七尺など、さまざまな故実を披露する逸話が載ります。
<文献>
『新儀式』
「野行幸事 若有野行幸、冬節行之。(中略)御輿入自日華門供之<中少将供奉如常、承平七年例、駕輿丁着両面帽子桃染衣、而延喜十七年、依不供野御輿、不用別装束。同十八年、延長六年等、皆用尋常御輿、駕輿丁如例>。乗輿出御(中略)次入御野中、儲軽幄於船岡下、其儀且同延喜十七八年、延長六年幸大原野。(中略)御酒三献之後、着御直御衣、更亦御輿入御野中覧猟、此間猟徒有献獲物者、又或上岡御覧四方、所司立御倚子於岡上、随便敷縁道属軽幄、近衛次将執御剣璽仕候、更還御軽幄、御厨子所供御酒、召侍臣堪事者、令調所献獲物雉等、供御膳、又給王卿以下等。」
『吏部王記』 (重明親王)
「延長六年十二月五日。(中略)大原野行幸。卯初上御輿。自朱雀門至五条路西折。到桂河辺。上降輿就幄。(中略)料理鷹人所獲之雉。殿上六位舁俎具。御厨子所進御膳御台二基。蔵人頭時望朝臣陪膳。侍従以衡賜王卿饌。侍従手長益送。六条院(宇多上皇)被貢酒二荷。炭二荷。火爐一具。殿上六位舁之御前。即解一瓶。至雉調所充供御、充公卿料。近衛将監役之。」
『小右記』(藤原実資)
「寛仁二年十月廿二日、辛亥。今日幸上東門院。(中略)次寄御輿<鳳輿。節会及元三行幸供鳳輿、臨時行幸供葱花輿。近代不被尋旧例、只供鳳輦耳>。」
『徒然草』
「鯉ばかりこそ、御前にても切らるゝものなれば、やんごとなき魚なり。鳥には雉、さうなきものなり。雉・松茸などは、御湯殿の上に懸りたるも苦しからず。」
「岡本関白殿、盛りなる紅梅の枝に、鳥一双を添へて、この枝に付けて参らすべきよし、御鷹飼、下毛野武勝に仰せられたりけるに、「花に鳥付くる術、知り候はず。一枝に二つ付くる事も、存知し候はず」と申しければ、膳部に尋ねられ、人々に問はせ給ひて、また、武勝に、「さらば、己れが思はんやうに付けて参らせよ」と仰せられたりければ、花もなき梅の枝に、一つを付けて参らせけり。武勝が申し侍りしは、「柴の枝、梅の枝つぼみたると散りたるとに付く。五葉などにも付く。枝の長さ七尺、或は六尺、返し刀五部に切る。枝の半に鳥を付く。付くる枝、踏まする枝あり。しじら藤のわらぬにて、二ところ付くべし。藤のさきは、ひうち羽の長にくらべて切りて、牛の角のやうにたわむべし。」
『村上天皇御記』
「康保元年二月五日壬子。為平親王遊覧北野。子日之興也。平旦天陰。及午尅漸晴。同刻召為平親王。参議伊尹朝臣於前。又召覧陪従殿上侍臣鷹飼等被馬。四位着直衣、五位着狩衣、鷹飼四人着野装束。又召従親王小童三人。其騎馬等同覧。未刻許。為平親王。使蔵人所雑色藤原為信。献鮮雉一翼。助信朝臣所捕獲云々。」
『遊庭秘抄』
「付様は鷹飼のとし葉に雉付たるにおなじ。五尺の枝に付枝と号してより三尺の枝にしんの枝かけて結付て。又下より一尺五寸に最下の枝と号して小枝一有べし。」
『四条流庖丁書』
「鷹ノ鳥ニハ如何ナル白鳥成トモ上ヲスベカラズ。雉ノ鳥ニ必可限。何ニテモ鷹ノ取タル鳥ヲバ賞翫勝タルベシ。鷹ノ鳥ヲ人ニ参ラスル時ニハ焼物ヨリ外ニスベカラズ。余ノ御肴ニ組付ル事スベカラズ。」

〈原文〉
[御装束心ことにひきつくろひて、御前などもことことしきさまにはあらで渡りたまふ。君達いとあまた引きつれて入りたまふさま、ものものしう頼もしげなり。丈だちそぞろかにものしたまふに、太さもあひて、いと宿徳に、面もち、歩まひ、大臣といはむに足らひたまへり。葡萄染の御指貫、桜の下襲、いと長うは裾引きて、ゆるゆるとことさらびたる御もてなし、あなきらきらしと見えたまへるに、六条殿は、桜の唐の綺の御直衣、今様色の御衣ひき重ねて、しどけなき大君姿、いよいよたとへむものなし。光こそまさりたまへ、かうしたたかにひきつくろひたまへる御ありさまに、なずらへても見えたまはざりけり。」
〈現代語訳〉
(内大臣は身なりを特に整えて前駆などはわざと簡単にして三条の宮へはいった。子息たちをおおぜい引きつれている大臣は、重々しくも頼もしい人に見えた。背の高さに相応して肥った貫禄のある姿で歩いて来る様子は大臣らしい大臣であった。紅紫の指貫に桜の色の下襲の裾を長く引いて、ゆるゆるとした身のとりなしを見せていた。なんというりっぱな姿であろうと見えたが、六条の大臣は桜の色の支那錦(しなにしき)の直衣の下に淡色(うすいろ)の小袖を幾つも重ねたくつろいだ姿でいて、これはこの上の端麗なものはないと思われるのであった。自然に美しい光というようなものが添っていて、内大臣の引き繕った姿などと比べる性質の美ではなかった。)
源氏の訪問を受けた三条の大宮は息子の内大臣を呼び出します。恰幅よく「宿徳(しゅうとく)」らしい威厳のある姿の内大臣がやってきました。「宿徳」とは修行を積んだ者、高位高官の高齢者という意味ですが、「どっしりしている」ことも指し、古典文学では太っていることの描写によく登場します。
内大臣の服装は「葡萄染の指貫に桜の下襲」です。袍についての説明がないので、位袍を着た「布袴(ほうこ)」であるのか雑袍(直衣)を着た「直衣布袴」であるのかは、にわかには判断できません。『花鳥余情(かちょうよせい)』では直衣布袴であると断じていますが、呼び出された事情をあれこれ推量して「御装束心ことにひきつくろひて」選んだことを考えると、よりフォーマルな位袍の布袴であったかもしれません。
それは源氏のラフな姿との対比にもなります。源氏は若い時代の「花宴」の帖にも見られる「桜の唐綺の直衣に今様色の御衣」姿。下襲の描写がないので直衣布袴ではなく通常の直衣姿に読めます。これが「しどけなき大君姿」とされますので、大君姿は直衣布袴とイコールではないことになりますが、「花宴」では「葡萄染の下襲、裾いと長く引きて」の直衣布袴を「あざれたる大君姿」としていて、これも判断が難しいところです。
<文献>
『小野宮年中行事』
「天皇御葱花輿。幸大極殿。後大臣召外記。令召使王。王進候膝突。大臣給宣命。或時第一上卿不動座而示次上令給宣命。是宿徳上卿之所存也。」
『三内口訣』
「必束帯之時。老若着下沓候。指貫之時ハ。足不見候条。不着韈候。但五六十以後宿徳ハ。衣冠直衣ニモ着下沓候。雖然御免申請義無之候。以此准拠存候時御免候沙汰不審候。」
『花鳥余情』 (一条兼良)
「えひそめの御さしぬき(中略)直衣布袴也。桜の下かさねは面白うらゑひそめなり(中略)六条殿はさくらのからきの(中略)これは布袴とはみえす。いまやう色の御そはつねのきぬなり。下かさねとはみえ侍らす。」
『源氏物語』(花宴)
「御装ひなどひきつくろひたまひて、いたう暮るるほどに、待たれてぞ渡りたまふ。桜の唐の綺の御直衣、葡萄染の下襲、裾いと長く引きて。皆人は表の衣なるに、あざれたる大君姿のなまめきたるにて、いつかれ入りたまへる御さま、げにいと異なり。」

〈原文〉
「かくのたまふは、二月朔日ころなりけり。十六日、彼岸の初めにて、いと吉き日なりけり。近うまた吉き日なしと 勘へ申しけるうちに」
〈現代語訳〉
(これは二月の初めのことである。十六日からは彼岸になって、その日は吉日でもあったから、この近くにこれ以上の日がないとも暦の博士からの報告もあって……)
当時の女子の成人式にあたるのが「裳着」です。結婚するにも宮仕えするにも、まず裳着を行って成人する必要がありました。玉鬘の気持ちが宮仕えに傾いたことを見抜いた源氏は「とてもかうても、まづ御裳着のことをこそは」と、まず裳着を済ましてしまおうと計画します。源氏は、藤原氏の血を引く玉鬘を源氏の子としては、藤原氏の氏神である「春日の神の御心違ひぬべき」として、最も重要な腰結役を内大臣に頼むことにしました。
その裳着の日程を「いと吉き日」として春の彼岸の初めの日に設定しました。春の彼岸は春分の日をはさんで前後三日、合計七日間がそれに当たります。「総角(あげまき)」の帖にも「彼岸の果てにて、吉き日なりければ」とありますが、古典文学の世界では『宇津保物語』などでも「彼岸の程によき日を取りて」などと表現され、彼岸は「お日柄も良い」日程とされていたようです。
平安後期には、彼岸の期間に仏事が行われたことが 『台記』や『兵範記』に見られますが、「懺法(せんぼう)」(知らないうちに積もった自らの悪行を懺悔して、心の中の「むさぼり・怒り・愚痴」の三毒を取り除き、心を静め清らかにする)が中心で、先祖供養的な意味はほとんど見られません。春分・秋分は太陽が真東から昇り真西に沈む特別な日。太陽を信仰した日本人が特別な意味を持つ縁起の良い日と考えたことは想像に難くないことです。
<文献>
『宇津保物語』(国譲下)
「彼岸の程によき日を取りて、さるべき事、思し設けて、大臣に忍びて物せん。」
『河海抄』(四辻善成)
「春中秋中昼夜各五十剋を時正といふ也。仍吉日たる歟。」
『台記』(藤原頼長)
「久安六年二月十九日、丙寅。(中略)自今日七ケ日〈彼岸〉潔齋〈夜前沐浴後、服浄衣居浄筵〉。於二不動尊銀三寸像〈件像、去十二日鋳造之(略)〉。(中略)祈請七ケ日之内〈自今日到廿五日〉、可蒙立后宣旨之由〈書願趣、納本尊御身〉。又七箇日、日別読心経廿一巻〈雖有過日、無不足日〉。奉春日祈請同事。」
『兵範記』(平信範)
「仁平三年二月廿三日、壬午。天晴、彼岸初也。「高陽院於白川御所被行恒例御懺法。下官奉行。寝殿中央母屋敷錦地鋪。立大壇安御経筥。在天蓋。其東間奉居釈迦三尊。大壇西間立七宝御塔。大壇前立前机。礼盤磬台等如常。南庇敷僧座帖三枚。立経机六前。他事如例。未及委記。」

〈原文〉
「かくてその日になりて、三条の宮より、忍びやかに御使あり。御櫛の筥など、にはかなれど、ことどもいときよらにしたまうて、御文には『聞こえむにも、いまいましきありさまを、今日は忍びこめはべれど、さるかたにても、長き例ばかりを思し許すべうや、とてなむ。あはれにうけたまはり、あきらめたる筋をかけきこえむも、いかが。御けしきに従ひてなむ。
ふたかたに言ひもてゆけば玉櫛笥 わが身はなれぬ懸子なりけり』」
〈現代語訳〉
(十六日の朝に三条の宮からそっと使いが来て、裳着の姫君への贈り物の櫛の箱などを、にわかなことではあったがきれいにできたのを下された。手紙を私がおあげするのも不吉にお思いにならぬかと思い、遠慮をしたほうがよろしいとは考えるのですが、大人におなりになる初めのお祝いを言わせてもらうことだけは許していただけるかと思ったのです。あなたのお身の上の複雑な事情も私は聞いていますことを言ってよろしいでしょうか、許していただければいいと思います。
ふたかたに言ひもてゆけば玉櫛笥 わがみはなれぬかけごなりけり)
裳着の儀式に際して、さまざまな女性たちから装束や調度品が贈られました。三条の祖母大宮からは「尼の身で憚られますが長寿の例として」と「櫛笥(くしげ)」が贈られます。これは文字どおり櫛などを入れる手箱で、いわゆる「玉手箱」のようなものです。「笥」は古代は食器のことでしたが、平安時代では「容器」のような意味になっています。実際には「櫛筥」と呼ばれるほうが普通で「櫛笥」は古風な表現だったようです。
「懸子」というのは箱の縁に懸ける底の浅い内箱のこと。玉鬘は自分の「孫」だということに掛けているのです。源氏は「よくも玉櫛笥にまつはれたるかな。三十一字の中に、異文字は少なく添へたることの難きなり」と歌を褒めます。
なお内裏・貞観殿の中にあった女蔵人の詰め所は「御櫛笥殿」と呼ばれ、そこで御服の裁縫をしていました。「御匣殿」とも書かれます。
<文献>
『延喜式』(内匠)
「年料(中略)櫛筥四合<各長一尺一寸五分。広一尺三寸。深一寸五分>。」
『類聚雑要抄』
「母屋机足二階厨子一脚<蓋手筥一双。次階櫛筥一双>。」
「二階厨子一双<東厨子上層置香壺筥一双。下層置櫛筥一双。西厨子上作子筥一双。下層置糸筥一双>。」
「東厨子上層置香壺筥一双。下層置櫛筥一双。」
『西宮記』(源高明)
「所々事(中略)御櫛笥殿<在貞観殿中、以上臈女房為別当、有女蔵人>。」
「賀茂臨時祭(中略)当日、召馬寮綱、西面懸装束、使賜御衣<櫛笥殿進之>。」

〈原文〉
「常陸の宮の御方、あやしうものうるはしう、さるべきことの折過ぐさぬ古代の御心にて、いかでかこの御いそぎを、よそのこととは聞き過ぐさむ、と思して、形のごとなむし出でたまうける。 あはれなる御心ざしなりかし。 青鈍の細長一襲、落栗とかや、何とかや、昔の人のめでたうしける袷の袴一具、紫のしらきり見ゆる霰地の御小袿と、よき衣筥に入れて、包いとうるはしうて、たてまつれたまへり。」
〈現代語訳〉
末摘花夫人は、形式的に何でもしないではいられぬ昔風な性質から、これをよそのことにしては置かれないと正式に贈り物をこしらえた。愚かしい親切である。青鈍色の細長、落栗色とか何とかいって昔の女が珍重した色合いの袴一具、紫が白けて見える霰地の小袿、これをよい衣裳箱に入れて、たいそうな包み方もして玉鬘へ贈って来た。
常陸宮の姫である末摘花は古風で生真面目な性格なので、こうした儀礼を無視はできないと、型のごとく玉鬘へ装束を贈ります。ところがその装束が源氏の失笑を買うことになる噴飯物なのでした。
まず若い女子の装束とされる細長ですが、その色彩が「青鈍(あおにび)」。これは喪に服する者や尼が用いることの多い色で、裳着のような祝儀にはふさわしくありません。『枕草子』には「青鈍色の指貫」が複数登場しますが、これも仏事に際しての着用例です。
落栗色の「昔の人のめでたうしける袷の袴」については、『紫明抄』に「こき紅の袴」とあるように、祝儀の袴の色「濃色(こきいろ)」と考えられます。平安後期の五節舞姫や婚儀では、女子の濃袴の記録が多く見られますので、特に「昔の人」とされるような物とも思われませんが、紫式部の時代にはそうした認識だったのでしょうか。
「紫のしらきり見ゆる霰地(あられじ)の御小袿(こうちぎ)」は『河海抄』では紫の白ばんだ色で、よろしくない色と説明しています。末摘花は初登場の「末摘花」の帖でも「聴し色のわりなう上白(うわじら)みたる一襲(ひとかさね)、なごりなう黒き袿」を着ていると描かれていますが、物語最後の登場となるこの場面でもまた、同じようなファッション感覚です。なお「霰地」とは市松文様のことです。
<文献>
『西宮記』(源高明)
「心喪装束。綾冠、綾袍、青朽葉、青鈍袴等也。或用无文冠、除重服之後一月着軽服。」
『助無智秘抄』
「有心喪人アヲニビ(青鈍)ノ織物。表袴。綾ノ柳色ノ下重ヲキル。夏ノ時ハアヲニビヲキルベシ。綾ノキヌマジヘテコレヲ用井ル。」
『餝抄』(中院通方)
「保安四年二二新院始御幸。御奴袴半色二重織物。鸚鵡唐草白丸文。無文青鈍奴袴。」
『紫明抄』(素寂)
「おちくりとかやなにとかやむかしの人のめてたくしけるいろあひ
こき紅の袴也」
『河海抄』(四辻善成)
「落栗色<こき紅也。合袴は中重のなき袴也。うつほの物語にもあまたあり>。」
『花鳥余情』 ( 一条兼良)
「こき紅のくろみ入たるほとにそめたるをいふへし」
『満佐須計装束抄』(源雅亮)
「姫君の装束。丑の日。赤色の織物の唐衣。地摺の裳。蘇芳の袙一重。青き単もしは濃単。濃袴。赤色の扇。七尺の鬘唐物。」
『名目抄』
「濃色(コヒイロ)<十五未満用之。染色ハフシカネ染也。織物経緯共濃紫>。」
『装束集成』
「女房御装束事。永暦二正廿九、月輪殿中納言中将嫁娶姫君事、白御衣八、濃色御単、濃打御衣、薄蘇芳二重織物表着<亀甲文>、濃蘇芳二重織物、小打着<同文>、濃張袴。元永元十廿二、内大臣嫁娶<民部卿長安、生年廿九>、白衣八、濃単衣、濃袴、蒲萄染二重織物小褂。」
『台記別記』(藤原頼長)
「久安六年正月十九日丁酉(中略)此間三位整衣裳<蘇芳織物衣八領、青単萌黄二重織物五重、表著濃打衣、赤色織物五重、唐衣、白羅裳、濃袴。是入内夜皇太后所賜之装束也。」
『兵範記』 (平信範)
「久寿三年二月廿八日庚子(中略)、申剋許向權弁亭、於四条東洞院新造家被経営也。右衛門佐光宗令嫁第三女子也。(中略)上﨟女房二人(中略)已上皆著濃袴。童女二人蘇芳衵五、青単、濃打衵、濃袴等著之。」
『河海抄』(四辻善成)
「紫のしらみたる色歟、よからぬ色たる歟。うはしらみとかきたる本もあり。」
『岷江入楚』(中院通勝)
「紫の白らみきばみたる色歟、よからぬ色たる歟、うはしらみと書たる本もあり、しらみ、くろみたる色也、下を薄紅にそめて、上を紅に染たるなり、其色のそこねたるなり、紫のしらみたる色なり、是は落栗色の注也、或説に、下地を薄紫に染て、上を紅にてそめたる色也云々。弄花抄云、紫のしらみ、きばみたは、落栗色の程也云々、然共霰地の小褂の色と見るべき歟。」
『源氏物語』(末摘花)
「聴し色のわりなう上白みたる一襲、なごりなう黒き袿重ねて、表着には黒貂の皮衣、いときよらに香ばしきを着たまへり。」

〈原文〉
「御小袿の袂に、例の、同じ筋の歌ありけり。『わが身こそ恨みられけれ唐衣 君が袂に馴れずと思へば』御手は、昔だにありしを、いとわりなうしじかみ、彫深う、強う、堅う書きたまへり。(中略)「あやしう、人の思ひ寄るまじき御心ばへこそ、あらでもありぬべけれ」と、憎さに書きたまうて、「唐衣また唐衣唐衣 かへすがへすも唐衣なる」
〈現代語訳〉
小袿の袖の所にいつも変わらぬ末摘花の歌が置いてあった。
わが身こそうらみられけれ唐ごろも 君が袂に馴れずと思へば
字は昔もまずい人であったが、小さく縮かんだものになって、紙へ強く押しつけるように書かれてあるのであった。源氏は不快ではあったが、また滑稽にも思われて破顔していた。「どんな恰好をしてこの歌を詠んだろう、昔の気力だけもなくなっているのだから、大騒ぎだったろう」とおかしがっていた。「この返事は忙しくても私がする」と源氏は言って、不思議な、常人の思い寄らないようなことはやはりなさらないでもいいことだったのですよ。と反感を見せて書いた。
からごろもまた唐衣からごろも 返す返すも唐衣なる
末摘花が裳着の祝いの品である小袿の袂に源氏宛ての「例の、同じ筋の」和歌を入れて送ってきます。末摘花は「末摘花」の帖で「唐衣君が心のつらければ 袂はかくぞそぼちつつのみ」、「玉鬘」の帖でも「着てみれば恨みられけり唐衣 返しやりてむ袖を濡らして」と詠んでいます。そしてまた今回、祝儀に相応しくない恨み節「わが身こそ恨みられけれ唐衣 君が袂に馴れずと思へば」を公文書のような形式で贈ってきたのです。状況にかかわらず空気も読まない歌を贈ってくることも非常識と言えますが、当時は和歌に唐衣を詠み込むのは古風なこと、もはや時代遅れなこととされたようです。
正装として用いる「唐衣」は奈良朝の女子が羽織った唐風の「背子(はいし)」が変形したものとされます。『枕草子』では襟を肩から落とした「着垂れたる」「脱ぎ垂れて」唐衣を着る描写があり、絵巻物でもそうした姿で描かれますが、奈良朝の「領巾(ひれ)」のようなイメージの演出であったとも考えられます。
源氏は「貴女の歌は唐衣ばかり」という露骨に皮肉る返歌を贈ろうとしますが、玉鬘は「そのような歌を返しては、私が常陸宮の姫君様をからかっているようでございます」と困り顔です。
<文献>
『枕草子』
「宮にはじめて参りたるころ(中略)唐衣着垂れたるほど、なれやすらかなるを見るもいとうらやまし。」
「清涼殿の丑寅の隅の(中略)御簾の内に、女房、桜の唐衣どもくつろかにぬぎたれて」
『和名類聚抄』
「背子 弁色立成云背子<和名加良岐沼>形如半臂無腰襴之袷衣也楊氏漢語抄云背子婦人表衣以錦為之領巾<日本紀私記云比礼>婦人項上餝也。」

※本文の『源氏物語』引用文は渋谷栄一校訂<源氏物語の世界>より
(GENJI-MONOGATARI (sainet.or.jp))
現代語訳は「源氏物語 全編」与謝野晶子訳(kindle版)より
次回配信日は、10月2日です。





