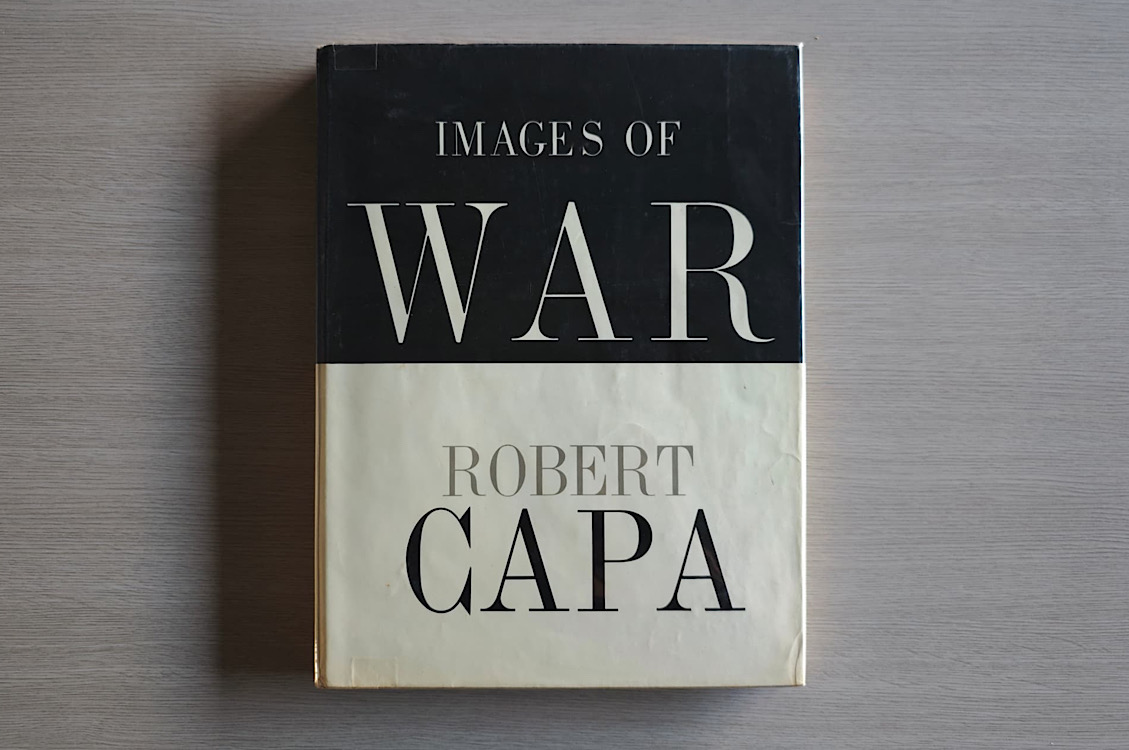木村さんは、一筋縄ではいかない人
1973年5月、木村伊兵衛さんに声をかけてもらって、日中友好撮影家訪中団に参加した。中国に対する戦争責任をめぐる反省によるものだったと思う。前年に日中国交正常化が実現して貿易と文化交流は再開されたたものの、中国は文化大革命の最中で、個人旅行は認められておらず、中国旅行なんて考えられない時代だった。私は旧満州の鞍山市で生まれていることもあり、中国には特別な思いがあったので、木村さんの誘いを二つ返事で受けたのだ。
前編でもお話ししたように、木村さんは1956 年の日本中国文化交流会発足と同時に常任理事になった。そして、63年、64年、65年、71年、73年の計5回中国を訪れ、北京、上海、蘇州、杭州、広州、⻑沙、⻄安、延安、洛陽などで撮影している。私が参加した73年の訪中団は、団長の木村さんをはじめ、篠山紀信、大倉舜二、木村さんの助手だった佐々木崑と薗部澄、田沼武能、写真界のお偉方や報道系の写真家など総勢11名。3週間にわたり中国各地で撮影をした。

外国人の行動は当局の管理下にあり、スケジュールは決められていた。団員の中には雑誌社から仕事をもらい、テーマを持って参加しているのに、次から次へ移動する団体旅行のためなかなか写真が撮れないと言う人もいた。不満が募り、それが木村さんにも聞こえてしまったようだ。
木村さんから集まって相談しましょうと声が掛かった。皆が集まると木村さんは開口一番、中国に対してものすごい剣幕で怒り出した。
「皆さん、忙しい中を無理して来ていただいたのに、こんないい加減な旅行はやっていられませんよ。私が皆さんの飛行機代を持ちますから帰りましょう」と。
すると、中国側の人たちも日本の人たちも、「まあまあ木村先生、そこまで言わずになんとか円満に」と言い出した。そういう状況を見て写真家たちも折れて旅を続けようと言い出した。木村さんはひと芝居打って、みんなの強張りをほぐしたのだ。
そのあと気分転換のため、みんなで近くにあった外国人観光客向けの友誼商店へ買い物に行くことになった。道すがら木村さんは、「北井さんにも参加費を払わせて来てもらって悪かったですね。やっぱり撮れませんか」と話しかけてきた。私は「これだけ大勢の人がいる場所へは来たことがないし、撮れすぎて、日本へ帰ったらどうやって写真集にするか考えているところです。自分は満州で生まれているし、本当に連れてきてもらってよかった」と感謝の意を伝えた。「そう言ってもらってほっとしました。これだけ街に人間がいて、写真が撮れないって、どういうことなんですかね」と何食わぬ顔で木村さんが言うのを聞いて、木村さんは「みんなは、テーマ主義すぎて撮れない」ということがわかっている、先の怒ったふりもそうだが、一筋縄ではいかない人だと実感した。

1973年の中国の旅での木村さんは、あまり調子がよくなさそうだった。木村さんは72歳だったはずだ。風邪を引いて熱が下がらず、ホテルで待っている日もあれば、外出しても、休み休みという時もあった。見るからに辛そうで、「カメラバッグを持ちましょうか」と伝えると、「持ってくれるの?」とすごく喜ばれてしまった。私は若かったので気楽に声をかけたのだが、他の人は畏れ多くて言い出せなかったのだと思う。
『木村伊兵衛写真集 パリ』の出版元になる
帰国後、木村さんから電話があった。
「のら社のようなストレートで分厚い写真集を作りたい。1950年代にパリで写したカラーフィルムがあるので、一度見てほしい」と相談されたのだ。これには心底驚いた。
のら社は、1970年に仲間たちと設立した写真集と書籍の出版社だった。きっかけを作ったのは、『アサヒグラフ』の敏腕編集者だった大崎紀夫さんだ。69年から数回にわたり三里塚芝山連合空港反対同盟の青年行動隊による座談会の記録が『アサヒグラフ』で掲載された。大崎さんは、その記録を本にしたいが、朝日新聞社ではできないから、お前がやってくれないかと私に話を持ちかけてきた。「三里塚」の連載をさせてもらっている大崎さんから言われたら断れない。集められたメンバーは、写真家の橋本照嵩と平地勲、和田久士、岡田明彦、広瀬渉。皆、『アサヒグラフ』に関わっていた。そして私は大崎さんから、代表をやれと指名され、77年まで務めることになる。
木村さんは電話で次のように語った。
「のら社が作る写真集をよく見せてもらっている。北井さんの『三里塚』と橋本照嵩さんの『瞽女』、どちらもストレート写真ですごくいい。これまでの僕の写真集は、テクニックを主体に編集されている。僕自身は、ストレート写真が一番いいと考え、パリも秋田もそのことを心がけて撮影した。写真集にする際、ストレート写真だけで構成したいと要求すると、それじゃダメだと編集者に説教されてしまうのだ。のら社の写真集を見て、自分はこれがやりたかったんだとはっきりわかった」
私は、準備ができたら写真を見せてもらいに伺いますと約束をして電話を切り、のら社の面々に相談をすることにした。大崎さんは、先に木村さんから話を聞いていて、「直接、北井に相談してほしい」と伝えたということだった。他のメンバーは、雲の上の人だった木村さんからの望外な依頼に意表を突かれながらも、自分たちも写真集を作ることに慣れてきたので、やってみようということになった。

木村さんから預かったのは、段ボール3箱にぎっしり入ったカラーポジフィルムだった。構成は、大崎さんにやっていただいた。B5判、カラー360頁の写真集のためにセレクトした中には、名人芸としての写真は一枚もなく、被写体をしっかりとらえた存在感のある写真だけが並んでいた。木村さんに、構成どおりの順で写真をお見せすると、「いいですね、いやよく、やってくれた。僕はこういうのがずっとやりたかったんですよ」と、ものすごく喜んでくれた。そして、「おそらく写真集は売れにくいだろう。ニコンやライカに僕から頼むから、売り先は心配しなくてもいい」と言って僕らを安心させてくれた。
ところが数日後の74年5月31日、木村さんは亡くなってしまった。奥様からも、「医者が大丈夫と言った」と聞いていただけに、木村さんの死は受け入れ難いものだった。しかも、木村さんから『パリ』の出版を引き受けたのだ。さて、どうするか。
写真集は印刷前だったので、ここで手を引くこともできる。のら社一同で話し合った。3000部印刷すると制作費は750万円ほどになる。額が大きすぎるし、木村さん本人がいなければ、きっと売れないだろう。しかし、みんなで木村さんに会いに行き、あんなに喜んでくれたのを目にしている。ここでやめたら後悔の念が生涯つきまとうだろう。若かった私たちは、あまり迷わずに出版を決めた。そして、それぞれ親に金を無心するなどして資金をかき集めた。和田久士や岡田明彦、杉山京子といった、当時20代半ばの若いメンバーも費用を負担してくれた。

『木村伊兵衛写真集 パリ』が完成すると、予想外なことに大きな話題となった。新聞各社が取り上げ、「これまでにない木村伊兵衛の写真集だ」と高評価し、安岡章太郎や原弘も書評を寄せてくれた。そのおかげで定価9000円という当時としては高額な写真集だったにもかかわらず、書店でもよく売れたのだった。一方、木村さんが声をかけると言っていたニコンやライカからの購入はなかった。あえて木村伊兵衛の名人芸を省いたことで、「これは木村伊兵衛じゃない」と、気に入ってもらえなかったのだ。そうした中で、「北井くん、よくやったね」と20冊買ってくれたのが日本大学に芸術学部写真学科を創設し、のちに同大の学長になった金丸重嶺だった。
「写真は芸術じゃない。私は職人です」
木村さんは亡くなる間際に、写真家として大変身を遂げた。それを後押ししたのが、のら社から出版した『木村伊兵衛写真集 パリ』だったと自負している。そこに写された写真は、人の存在感に重きを置いた、ストレート・フォトグラフィの魅力に溢れている。
「アサヒカメラ」での木村さんの最後の連載「街角」は、私の好きなシリーズだ。見舞いに来た人や、自分が寝ている部屋の壁に掛かっている時計、病室の窓から見た犬と散歩している風景などが切り取られている。「体が動く限り撮り続けたい」という意志があった木村さんは、ストレートで素朴な写真表現でそれを実践したのだ。

木村さんは、「写真は芸術じゃない。ストレートなものこそ写真だ。私は職人です」と言い切っている。写真は絵や彫刻と違い、ゼロからつくりあげるものではない。そこが絵や彫刻との大きな違いだと思う。木村さんは、「写真は印刷物になってはじめて価値がある。大衆の中にあるのが一番いいものだ」とも語っていた。木村さんの写真プリントは名人芸の極致だった。木村さんは粉を溶いてつくった液で現像していくのだが、ほとんどの写真家は真似のできない見事さだった。けれども木村さんは、オリジナルプリントの価値を認めていなかった。
私は、木村さんがご自宅で自分のプリントを焼却する現場を目撃したことがある。のら社の連中と木村さんの家を訪ねたちょうどその時、木村さんはプリントを焼却し終えて庭から上がってきたのだ。そして私たちに、「あー清々した。こんなものを残して死ねるか」と言ったのだ。その言葉には、江戸っ子の勢いと、写真への信念がこもっていた。
だから木村伊兵衛が自ら焼いたオリジナルプリントはものすごく少ないのだ。
今や、写真は芸術のひとつと位置づけられ、写真でアートを表現する傾向が高まっている。木村さんの思想や理念を受け継ぐはずの木村伊兵衛賞の受賞作品が、近年、芸術写真ばかりになっていることに、私は違和感を覚えている。
木村さんは、現実をしっかり見ていた。そして、特別な芸術性よりも、リアルな瞬間をとらえることに価値を置いた。木村さんが、「写真は芸術ではない」といった意味を今一度解釈しなおしてもいいのではないだろうか。